会社が受ける風評被害を理解しよう!原因と対策、知っておくべき事例など

「風評被害」は、一度発生してしまうとその影響は、売上減少や採用難など多岐にわたり、企業の存続を脅かしかねません。
しかし、風評被害は、その発生原因や種類を正しく理解し、適切な予防策を講じることで、リスクを最小限に抑えられます。
また、万が一風評被害が発生してしまった場合の対応策を知っておくことも、早期の鎮火と信頼回復に不可欠です。
この記事では、会社が受ける風評被害について、その基本的な概念から発生原因、中小企業が取るべき予防策と事後対応についてを網羅的に解説します。
目次
風評被害とは?基本を押さえておこう
企業や団体にとって、信頼はかけがえのない財産です。しかし、根拠のない噂や不確かな情報が広まることで、その信頼は容易に損なわれてしまいます。これが「風評被害」です。
ここでは、風評被害の基本的な意味合いから、そして類似する概念との違いまでをわかりやすく解説します。
風評被害とは?
風評被害とは、事実に基づかない噂やデマなどが広まることにより、企業や個人、地域などが経済的・社会的な損害を被る現象です。
英語では「reputational damage」や「rumor damage」と表現されます。
ネットやSNSの拡散力により、国境を越えて情報が拡散しやすいため、一つの国で発生した風評被害が、瞬く間に世界中に広がる可能性がある、リスクの高い現象です。
そのため、グローバルな事業展開を目指す企業はとくに、多言語に対応した情報発信やモニタリング体制の構築が必要となります。
風評被害と誹謗中傷の違いは?
風評被害と誹謗中傷は混同されがちですが、明確な違いがあります。
| 項目 | 風評被害 | 誹謗中傷 |
| 目的 | 悪意がある拡散 善意の誤解 無責任な情報拡散 | 特定の対象を貶める 精神的な苦痛を与える |
| 内容 | 不確か 真偽不明 憶測 事実を誇張 | 事実無根 歪曲 侮辱 プライバシー侵害 |
| きっかけ | 事故 事件 災害 企業の不祥事 誤った報道 SNSでの拡散 | 個人間のトラブル 競争関係 意見の対立 一方的な恨み |
誹謗中傷は、特定の対象を意図的に貶める悪質な書き込みや発言であり、名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があります。
一方、風評被害は、必ずしも悪意があるとは限らず、不確かな情報や憶測が広まることで発生するのが特徴です。ただし、中には悪意のある情報発信が風評被害を引き起こすケースも存在します。
風評被害が発生する原因は?
風評被害が発生するさまざまな原因を分類し、具体的な要因と発生しやすい状況・背景を以下にまとめました。
| 原因の分類 | 発生しやすい状況・背景 |
| 情報源の不確かさ | 情報公開の不足 透明性の欠如 コミュニケーション不足 災害や事故など混乱時 |
| 情報の歪曲・誇張 | 不安や不満の高まり 特定の意見への共感 扇動的な言動 SNSでの感情的な拡散 |
| コミュニケーションの失敗 | 緊急時や危機管理における対応の不備 メディアや関係者との連携不足 ステークホルダーへの配慮不足 |
| 社会情勢・心理 | 社会全体の閉塞感 経済状況の悪化 特定の事件や事故の発生 差別や偏見が存在する社会構造 過去のトラウマ |
| ネット・SNSの特性 | 情報リテラシーの低さ 感情的な反応の誘発 アルゴリズムによる情報の偏り 監視体制の不備 |
| 過去の出来事の影響 | 過去の信頼失墜 再発防止策の不徹底 風化していない記憶 |
| 競合他社・悪意のある第三者の意図 | 競争環境の激化 恨みや報復感情 経済的な利益を目的とした行為 |
風評被害は、単一の原因によって引き起こされるものではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生します。
風評被害の種類を把握する
風評被害は、その原因や情報の性質によってさまざまな様相を呈します。企業が適切な対策を講じるためには、どのような種類の風評被害が存在するのかを理解することが不可欠です。
代表的な風評被害の種類と、それぞれの事例について表にまとめました。
| 風評被害の種類 | 具体的な事例 |
| 根拠のない噂やデマによる風評被害 | 製品に有害物質が混入しているらしいという噂 店内が不衛生だという情報がSNSで拡散 |
| 過去の不祥事や事故による風評被害 | 過去に起きたデータ漏洩事件が再びSNSで蒸し返される 異臭により工場での過去の爆発事故が想起され、近隣住民からの不安の声が広がる |
| 誤った情報や憶測による風評被害 | 新サービスに関する誤った情報がネット記事で拡散され、問い合わせが殺到 社長のSNS投稿が一部切り取られ、意図と異なる解釈で批判が集中 |
| 意図的な悪評による風評被害 | 競合他社が匿名でネガティブな情報を掲示板に書き込む 元従業員がSNSで事実無根の告発を行い、炎上を誘発 悪意のある第三者が企業の評判を貶める目的で虚偽のレビューを大量投稿 |
近年はネット、SNSでの風評被害が増えており、加速度的に広まるため、以前よりも会社としての守りを強化することが必要です。
風評被害が中小企業にもたらす悪影響
中小企業にとって、風評被害は時に存続をも左右する深刻な問題へと発展する可能性があります。
大企業に比べて経営資源が限られている中小企業は、一度負の評判が広まってしまうと、その影響を食い止めることが困難になりやすいのです。
以下で、風評被害が中小企業にもたらす具体的な悪影響について解説します。
顧客離れと売上減少
風評被害の最も直接的な影響として挙げられるのが、顧客の減少とそれに伴う売上の低下です。
根拠のない噂やネガティブな情報が広まると、「品質が悪そう」「安全ではなさそう」といった不安が顧客の間に広がり、購買意欲を大きく損ないます。
とくに地域に根ざした中小企業の場合、口コミや評判が重要な集客手段となるため、一度悪い評判が定着してしまうと、その影響は長期にわたります。
風評被害による売上減少は、損害賠償請求の根拠となる可能性もありますが、立証は難しいでしょう。
採用活動への影響と人材流出
風評被害は、既存の従業員のモチベーション低下を招くだけでなく、新たな人材の採用活動にも悪影響を及ぼします。
「評判の悪い会社では働きたくない」と考える求職者が増え、応募者数の減少や採用難を引き起こすのです。
また、すでに在籍している従業員も、将来への不安や周囲からの評判を気にして離職を検討する可能性があり、貴重な人材の流出につながる恐れがあります。
金融機関からの信用低下
金融機関は、企業の信用力を融資の判断材料の一つとしています。風評被害が発生し、業績が悪化したり、将来への不安視が高まったりすると、金融機関からの信用評価が低下するかもしれません。
風評被害により、新たな融資が受けにくくなったり、融資条件が悪化したりするリスクが生じ、資金繰りの悪化を招くことがあります。
従業員のモチベーション低下
風評被害により、自社に対するネガティブな情報が広まっている状況は、従業員の士気を大きく低下させます。
「自分たちの会社は大丈夫なのか」「顧客からの信頼を失ってしまったのではないか」といった不安感が広がり、仕事への意欲を失わせる可能性があります。
また、顧客や取引先からの心ない言葉や態度に直面することで、精神的な負担を感じる従業員も出てくるでしょう。
従業員のモチベーション低下は、生産性の低下やサービスの質の低下につながり、さらなる風評被害を招く悪循環が生み出される可能性があります。
中小企業が風評被害を予防するための対策
風評被害は、発生してから対応するよりも、事前に予防策を講じることが重要です。とくに経営資源が限られる中小企業においては、事前の備えが事業継続を左右すると言っても過言ではありません。
ここでは、中小企業が風評被害を未然に防ぐために取るべき具体的な対策について解説します。
正確な情報発信と透明性の確保
日頃から以下のような正確で透明性の高い情報発信を心がけることは、風評被害の予防につながります。
- 企業の活動内容、製品やサービスの品質、安全性に関する情報を積極的に開示
- 公式サイトやSNSを活用し、最新情報をタイムリーに発信
- 問い合わせ窓口を設け、疑問や不安に対応できる体制
これらの対策により、不確かな情報や噂が広がる隙を与えないことが大切です。
リスクマネジメント体制の構築
風評被害を含むさまざまなリスクがあることを想定し、以下のような対応策を事前に準備しておくことが重要です。
- 拡散する可能性がある情報と影響範囲を分析し、具体的な対応フローを策定
- 緊急時の情報発信体制や責任者の明確化
- 定期的な見直しと訓練を実施
このような対策により、いざという時に迅速かつ適切な対応が可能になります。
SNSモニタリングの実施
近年、SNSは情報拡散の主要なプラットフォームとなっており、風評被害を防ぐには以下のような対策を実施することが求められます。
- 自社に関する投稿や言及を定期的にモニタリング
- ネガティブな情報や不確かな噂が広まっている場合は、火消しや事実に基づいた反論
こうした対策により、風評被害の拡大を防げます。SNSモニタリングツールを活用することも有効な手段です。
従業員への啓発活動
従業員一人ひとりの情報発信が、風評被害につながる可能性があるため、以下のような対策が必要です。
- SNSの利用に関するガイドラインの策定
- 不確かな情報や憶測に基づく発信を控えるような教育
- 自社の良い情報の積極的な発信促進
- ネガティブな情報を見つけた場合の報告ルート明確化
従業員全体で企業イメージを守る意識の向上が、風評被害の予防につながります。
風評被害保険の検討
万が一、風評被害が発生してしまった場合に備えて、風評被害保険の検討も有効な選択肢の一つです。風評被害保険の補償内容は主に以下になります。
- 売上減少
- 広告宣伝費の増加
- 専門家への相談費用
風評被害保険に加入しておくことで、経済的な負担を軽減し、早期の事業回復を図ることが可能になります。保険の内容や適用範囲を十分に理解し、自社の状況に合わせて検討しましょう。
風評被害が起きた際に中小企業が取るべき対応策
風評被害は、どんなに注意していても発生する可能性があります。ここでは、中小企業が風評被害に直面した際に取るべき具体的な対応策を段階的に解説します。
| 風評被害の対応策 | 具体的な行動 |
| 迅速な事実確認と情報収集 | 問題となっている情報の出所や内容などを迅速かつ正確に調査 関係者からのヒアリングや記録の確認を行い、客観的な事実を把握 オンライン上の情報も漏れなく収集 |
| 公式声明の発表と情報公開 | 事実確認に基づき、速やかに公式な声明を発表 誤った情報に対しては正確な情報を提示し、透明性のある説明 適切なチャネルを通じて情報を公開し、関係者の不安を解消 |
| 関係者への丁寧な説明と謝罪 | 関係各方面に対して状況の説明と、必要に応じて謝罪 相手に合わせた丁寧なコミュニケーションを行う |
| 弁護士や専門家への相談 | 法的な側面からのアドバイスや、風評被害対策の専門家への相談 専門的な知識や経験に基づいたサポートを受ける |
| ネット上の情報監視と対応 | 引き続きネット上の情報を監視し、新たな拡散や二次的な被害の発生を防ぐ プラットフォーム管理者への削除要請や、反論・訂正情報の掲載 |
| 損害賠償請求や法的措置の検討 | 悪質な風評被害に対しては、弁護士と相談の上、損害賠償請求や法的措置を検討 |
重要なのは、発生直後の迅速かつ適切な対応です。初期対応の成否が、被害の拡大を食い止め、早期の信頼回復につながります。
風評被害の具体的な事例
風評被害は、抽象的な概念として捉えられがちですが、実際にはさまざまな形で企業や団体に深刻な影響を与えています。
ここでは、過去に発生した具体的な事例を通して、風評被害がどのように広がり、どのような学びを得られたのかを明らかにします。
金融機関の風評被害事例:地方銀行
「某地方銀行が破綻する」というデマが流れました。その噂は広がりを見せ、多くの預金者が預金を引き出す事態となり、その額は数百億円にも上りました。
事例からの学び:
この風評被害の事例から企業として学ぶべきは、人々の冷静さを取り戻させるためには、信憑性があり、量的に充実した「情報」であるという点です。
正しい情報を提示することで、「短絡的な行動こそ自分にとってリスクである」と説得できれば、人々の冷静さを取り戻させることが可能です。
後日この銀行では、危機管理体制の甘さを認識し、危機管理マニュアルの改訂や連絡体制の見直しを図りました。
食品業界の風評被害事例:トマト農家
SNSを中心に「ワクチン入りトマトが出回っている」という情報が拡散され、これには10以上の大手食品企業が関与しているという内容も含まれていました。
この風評被害では、企業の信用が失われ、消費者の不安が広がり、製品の販売にも影響が出ました。
事例からの学び:
この事例から、企業が風評被害に対処するためには、迅速かつ正確な情報発信が重要であるとわかりました。また、SNSなどのソーシャルメディアの監視も欠かせません。
風評被害が発生した場合には、企業は積極的に情報を発信し、消費者の不安を解消することが大切です。
環境問題の風評被害事例:製油所
東日本大震災発生後、某石油製油所で火災が発生しました。その後、「製油所の爆発により有害物質が雨などと一緒に降るので、外出の際は注意が必要」といったチェーンメールが、インターネット上で広範囲に拡散されました。
このチェーンメールには、「工場勤務の親族からの情報」や「厚生労働省によると」といった信憑性を装う記述も見られたのです。
事例からの学び:
この事例から、災害時などの緊急時においては、不確かな情報が瞬時に広がる可能性があるとわかります。
企業としては、デマや不確かな情報が広まっていることを把握したら、速やかに公式な情報源から正確な情報を発信することが重要です。
火災の原因や状況、人体への影響に関する正確な情報を開示し、隠蔽しているような印象を与えないように努めなければなりません。
風評被害を防ぐため、緊急時においても迅速かつ適切に情報発信できる広報体制を、平時から整備しておくことが不可欠です。
まとめ
この記事では、会社が直面する可能性のある風評被害について、基礎知識から中小企業が講じるべき予防策と事後対応策を詳しく解説してきました。
風評被害は中小企業において、顧客離れや売上減少、採用活動への影響といった深刻な悪影響をもたらす可能性があります。
しかし、予防策を講じることで、そのリスクを低減し、万が一被害が発生した際には、迅速な事実確認や公式声明の発表などが重要となります。
過去の事例から学び、適切な対策を講じることで、風評被害から会社を守り、持続的な成長へとつなげられるのです。
関連記事
-
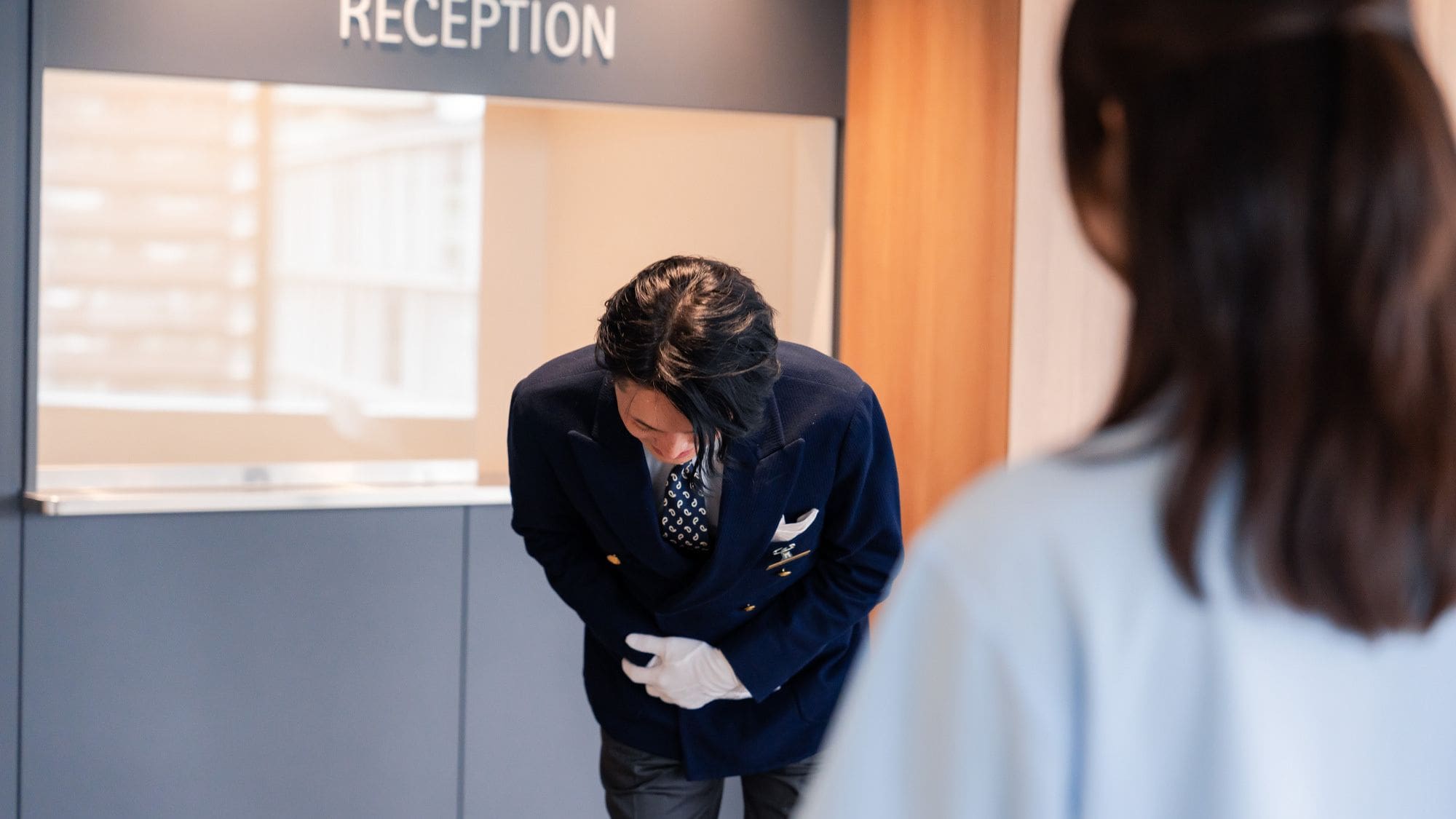
クレームと苦情の違いを理解しよう!言葉の意味、ビジネスシーンでの使い方など
中小企業の現場では、日々の業務の中で「クレーム」や「苦情」への対応を迫られることがあります。
しかし、それぞれの言葉の意味を正しく理解していないと、対応の方向を誤り、さらなるトラブルを招く恐れもあります。
本記事では、「クレーム」と「苦情」の本来の意味やビジネス上の違い、さらに中小企業が注意すべき対応のポイントまでを網羅的に解説します。組織の“守り”を強化するために、ぜひこの機会に理解を深めておきましょう。
-

悪い口コミで採用が止まる?会社ですぐにやるべき口コミ対策を解説
「自社の口コミがどうなっているか気になる」「もしネガティブな書き込みを見つけたら、どのように対応すれば良いのだろうか?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、会社の口コミを調べる方法や、万が一悪い口コミを発見した場合に取るべき適切な対応策、そして避けるべきNGな行動を詳しく解説します。
企業の評判を守り、より良い組織づくりと採用活動を推進するためにも、ぜひ参考にしてください。
-

クレーム対応の例文を紹介!メール・手紙、電話など手段ごとに解説
クレーム対応は、内容そのものだけでなく「どのように伝えるか」によって印象や信頼の行方が大きく変わります。
特に中小企業では、限られた人員で対応を行うことが多く、担当者ごとに表現がぶれてしまうケースも少なくありません。
本記事では、クレーム対応における基本的なマインドや5つの対応手順を整理したうえで、実際に使えるメール・手紙・電話の例文をシーン別に紹介します。属人化を防ぎ、組織としての対応力を高める第一歩として、ぜひ参考にしてください。
-
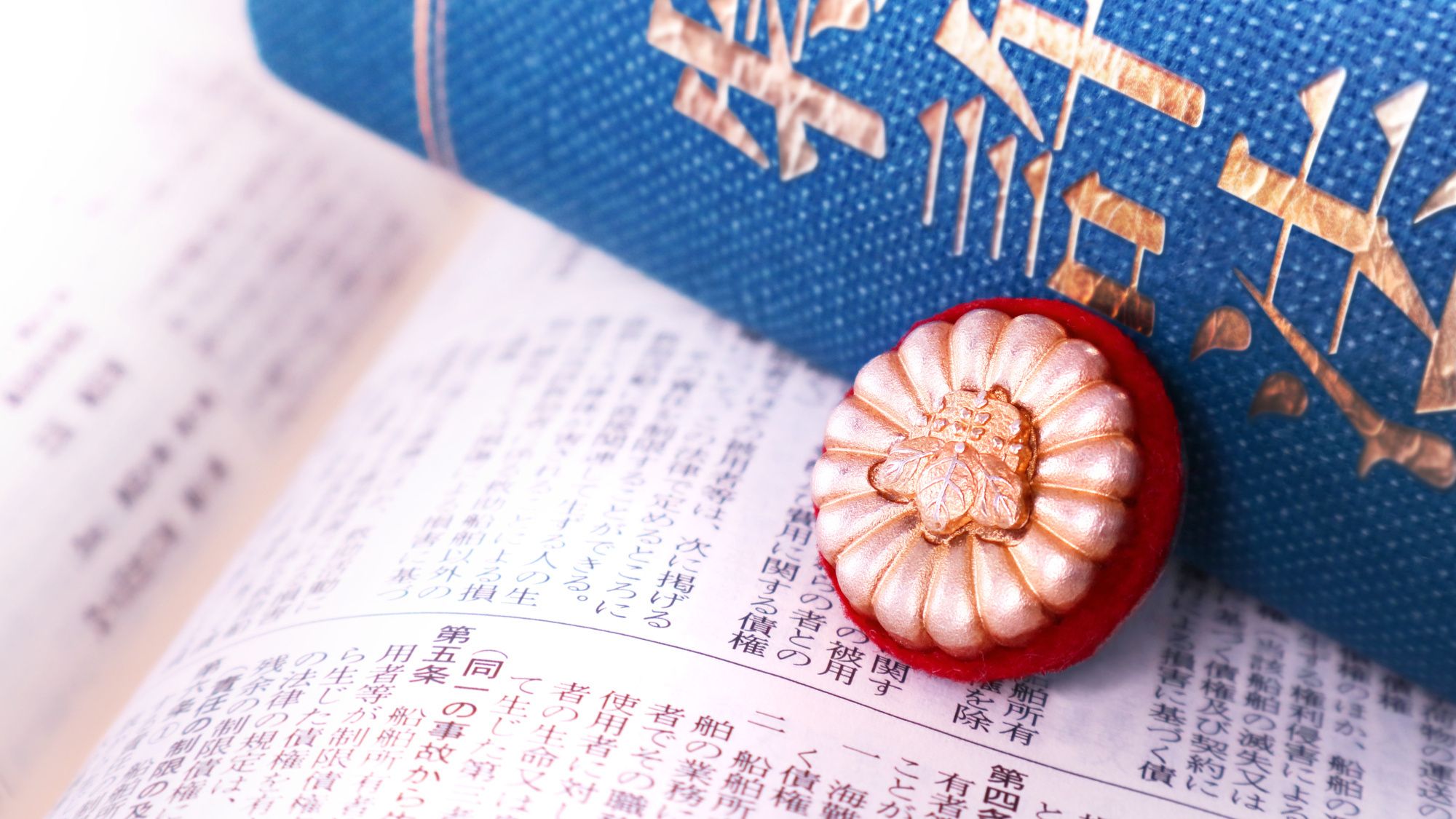
特許法とは?特許取得の要件やメリット、出願の流れをわかりやすく解説
自社で開発した画期的な技術やアイデアを守るのが特許法の役割です。
この記事では、特許法の基本的な考え方や、特許を取得するための具体的な要件、そして特許を持つことで得られるメリットをわかりやすく解説します。
また、万が一、他社の特許権を侵害してしまった場合、あるいは自社の特許権が侵害された場合の対策についても解説するので、自社の貴重な技術やアイデアを守り、ビジネスを有利に進めるためにもぜひ最後までご覧ください。
-
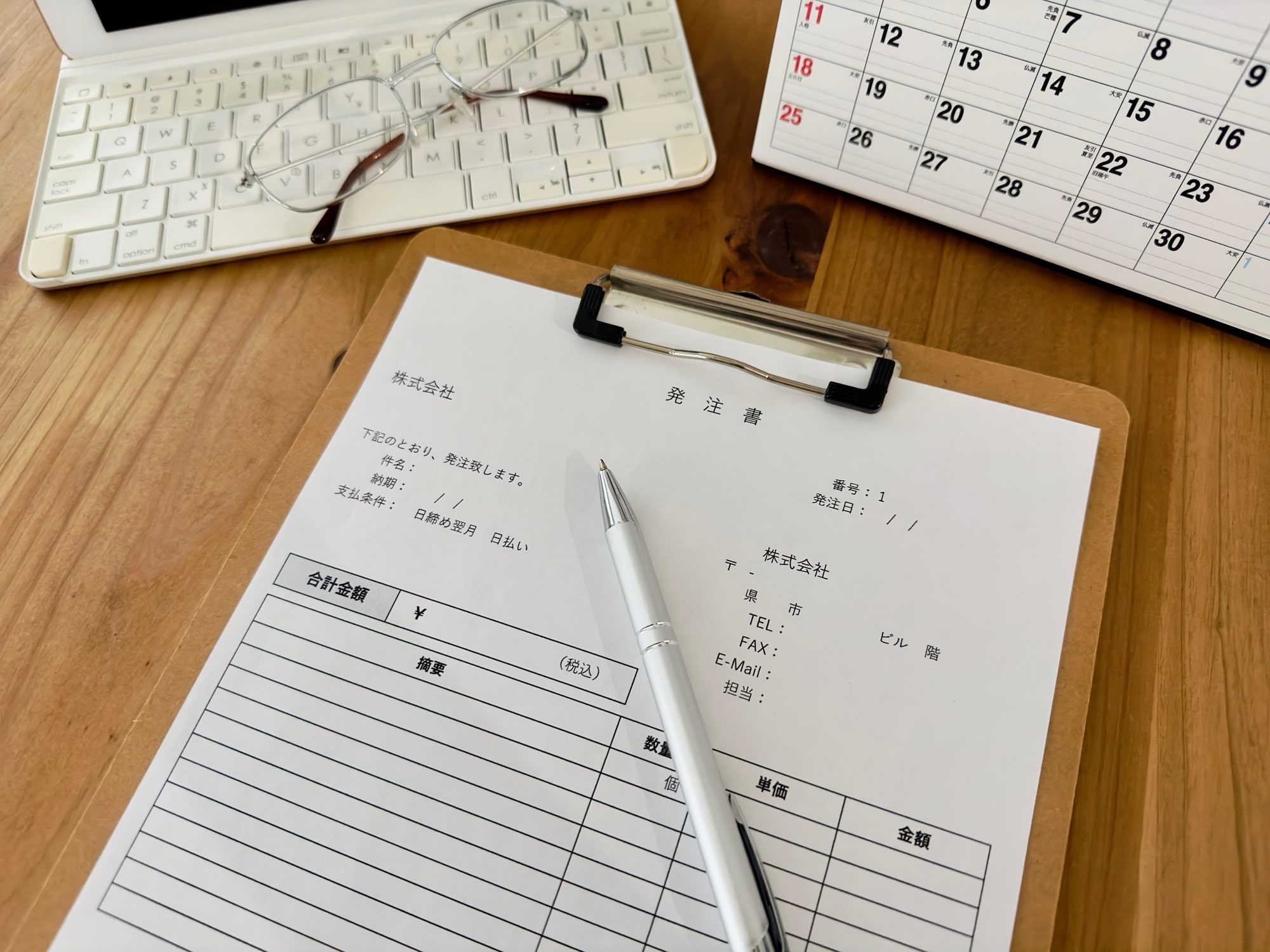
下請法の適用対象とは?資本金規模と取引条件を徹底ガイド
下請法は、親事業者と下請事業者間の公正な取引を確保するための重要な法律です。とくに、資本金の規模によって適用範囲が異なるため、要件を把握しておく必要があります。
この記事では、下請法の概要と資本金との関係、さらに違反を避けるための具体的なポイントなどをわかりやすく解説します。
下請法を正しく理解し、健全なビジネス環境を築きましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






