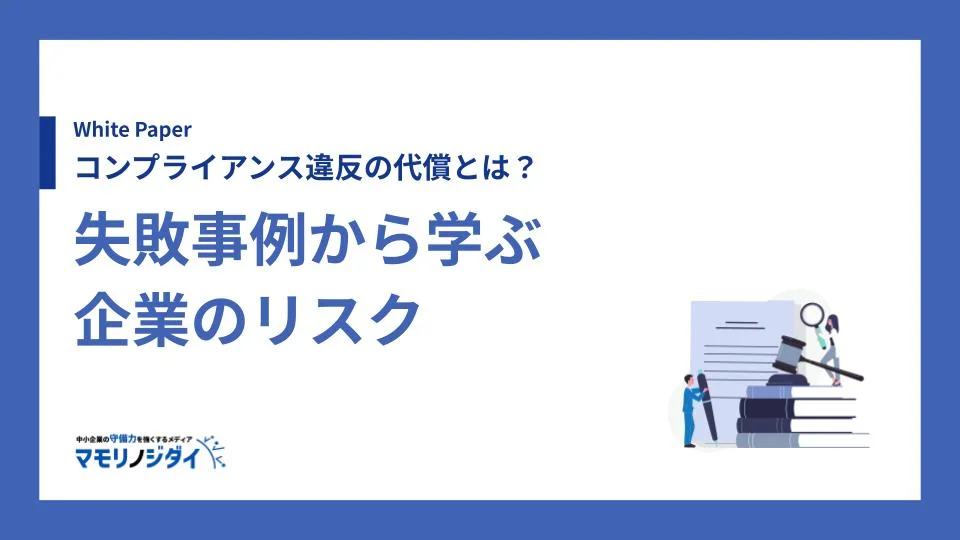中小企業が知っておきたい労働組合法をわかりやすく解説!気になる条文も紹介
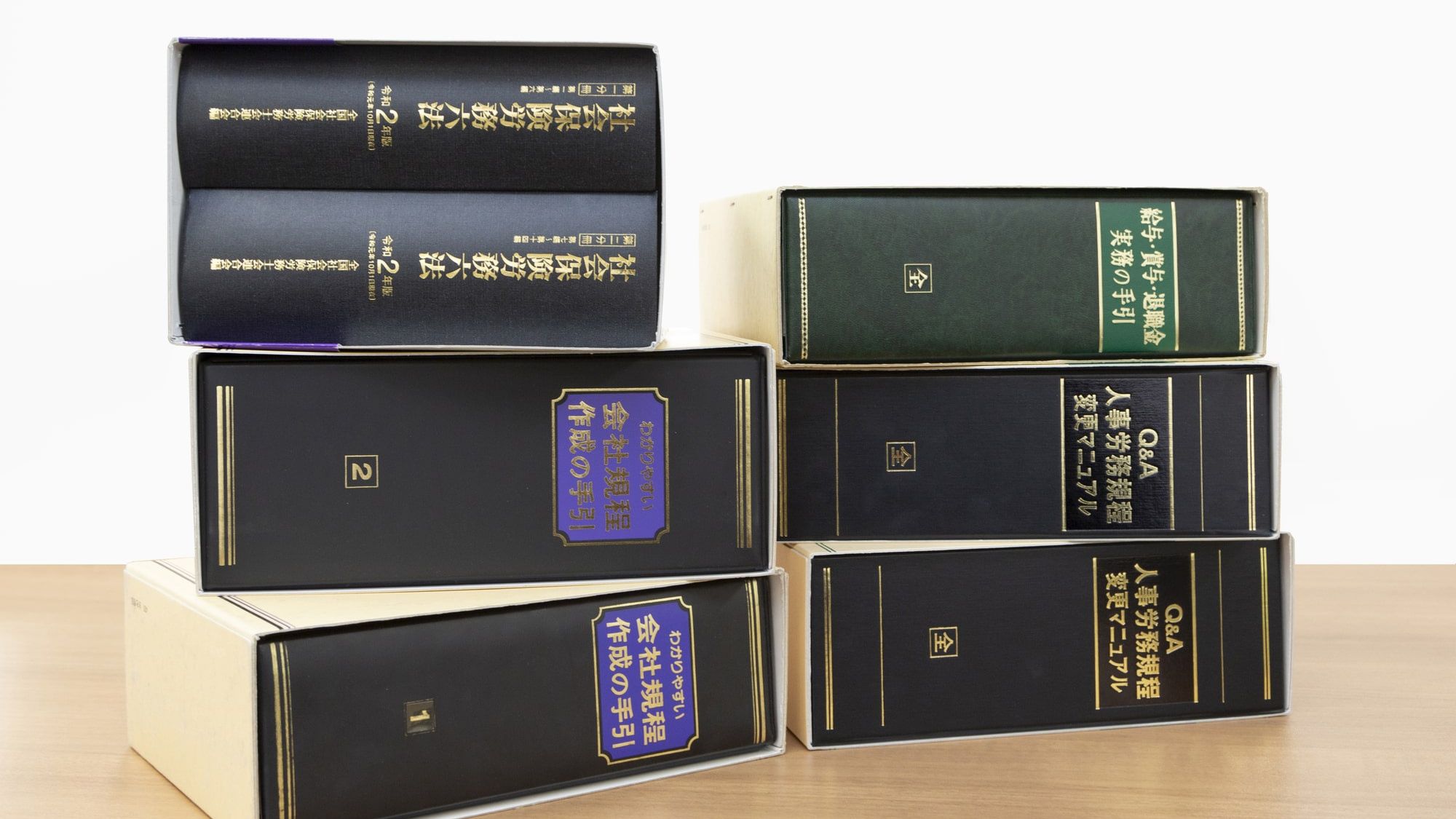
労働組合法は、労働者の権利を守り、使用者との健全な労使関係を築くために重要な法律です。しかし、中小企業においては、労働組合法に関する知識不足や誤解から、意図せず違反してしまうケースも少なくありません。
労働組合法違反は、法的リスクだけでなく、企業の社会的信用や従業員との関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事では労働組合法の基本から、とくに注意すべき条文、不当労働行為の具体例、違反した場合のリスク、そして違反を防ぐための対策について、わかりやすく解説します。
目次
まずは労働組合法を理解しよう!目的や背景など
労働組合法とは、労働者が団結して労働条件の改善や経済的地位の向上を図る権利を保障するための法律です。
1945年12月22日に公布され、1946年3月1日に施行されました。
参考)国立公文書館「昭和20年(1945)12月 労働組合法が制定される」
労働者の権利を守るための法律として、労働基準法、労働関係調整法と並んで「労働三法」の一つに数えられています。
労働組合法とは?
労働組合法は、労働者が使用者と対等な立場で交渉し、より良い労働条件を勝ち取るために制定されました。
具体的には、労働者が労働組合を結成し、使用者と団体交渉を行う権利、団体行動を行う権利などを保障しています。
また、使用者による不当労働行為を禁止することで、労働者の権利を保護しています。
労働者の権利を守るための重要な法律であるため、中小企業の経営者も、労働組合法の基本的な内容を理解しておく必要があるのです。
参考)e-Gov法令検索「労働組合法」
労働三法とは?労働基準法・労働関係調整法との違い
労働三法とは、労働者の権利を守るための重要な3つの法律、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の総称です。
それぞれの法律の目的と中小企業への影響を比較表にまとめました。
| 法律名 | 目的 | 中小企業への影響 |
| 労働組合法 | 労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、使用者との対等な交渉を促進 | 労働組合との団体交渉に応じる義務不当労働行為は禁止違反すると法的責任 |
| 労働基準法 | 労働条件の最低基準を定め、労働者を保護する | 労働時間、賃金、休日など、法律で定められた基準を守る違反すると罰則を受ける可能性 |
| 労働関係調整法 | 労働争議の予防と解決を促進し、労使関係の安定を図る | 労働争議が発生した場合、斡旋、調停、仲裁などの手続き |
これら3つの法律は、それぞれ異なる目的を持っていますが、労働者の権利を守り、労使関係の安定を図るという共通の目標を持っています。
中小企業の経営者も、これらの法律を正しく理解し、適切な労務管理を行うことが重要です。
労働組合法で押さえておきたい条文
憲法と労働組合法について、中小企業が注意したい条文に関する内容を以下で表にまとめました。
| 条文 | 中小企業が注意したい内容 |
| 憲法第28条(労働三権) | 労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は憲法で保障された権利であることを認識する |
| 労働組合法第2条(労働組合の定義) | 労働組合は、労働者が自主的に結成する団体であり、使用者から独立している必要がある |
| 労働組合法第6条(団体交渉権) | 労働組合は、使用者に対して団体交渉を要求でき、使用者は誠実に交渉に応じる義務がある |
| 労働組合法第7条(不当労働行為) | 使用者による不当労働行為(組合員差別、団体交渉拒否など)は禁止されている |
| 労働組合法第16条(労働協約の効力) | 労働協約は、労使間で締結された労働条件に関する協定であり、法的効力を持つ |
| 労働組合法第17条(経費の経理) | 労働組合の経費は、組合員が負担する組合費で賄われ、使用者からの寄付などは禁止されている |
参考)
e-Gov法令検索「日本国憲法」
e-Gov法令検索「労働組合法」
労働組合法の中でも、とくにこれらの条文を理解することで、労働者の権利を守る企業として認めてもらえるのです。
前提となる「労働組合」とは?
労働組合は、労働者が主体となって労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体です。
この労働組合の活動を保障する法律が「労働組合法」であり、労働基準法、労働関係調整法と並んで「労働三法」の一つに数えられています。
労働組合の主な目的と機能
労働組合法が保障する労働組合の主な目的と機能は以下の通りです。
| (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |
出典)e-Gov法令検索「労働組合法」
労働組合の目的をわかりやすくまとめると、以下3つになります。
労働条件の改善: 賃金、労働時間、休日などの労働条件について、使用者と交渉し、改善を目指す
交渉権: 労働者の代表として、使用者と団体交渉を行う権利を持つ
団結権の保護: 労働者が団結して労働組合を結成し、活動することを保護
労働組合の役割を正しく理解し、日頃から労働者とのコミュニケーションを密に取ることで、労働組合との協調的な関係を築くことが重要です。
参考)厚生労働省「労働組合」
経営者は「労働協約」についても知っておこう
労働協約とは、労働組合と企業の間で締結される合意事項を指します。
| (労働協約の効力の発生) 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 |
出典)e-Gov法令検索「労働組合法」
労働組合法第14条で定められており、労働条件や労働者の権利義務などについて、具体的な内容が定められます。
労働協約は、労働組合と企業の代表者が対等な立場で交渉し、合意した内容を書面にまとめたものです。労働協約が締結されると、その内容は労働組合の組合員だけでなく、企業全体の従業員に適用されます。
また、労働協約には法的拘束力があり、企業と労働者は協約の内容を守る義務を負います。
企業が労働協約を結ぶ際には、以下の点に注意しなければなりません。
労働組合との十分な協議を行うこと
労働協約の内容を明確かつ具体的に定めること
労働協約の内容が法令に違反していないか確認すること
労働協約は、労使関係をスムーズにするための重要なツールです。労働協約を適切に活用することで、企業は労働組合との信頼関係を築き、安定した労使関係を維持できます。
中小企業が理解すべき「不当労働行為」とは?
不当労働行為とは、労働組合法第7条で禁止されている、使用者が行ってはならない行為です。中小企業の経営者・バックオフィス担当者は、以下の行為に注意する必要があります。
| 労働組合法は、使用者による以下の行為を「不当労働行為」として禁止している。 a 労働組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱い(労働組合法第7条 第1号) [例] ・ 労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金 ・ 昇格の差別等 ・ 労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること b 正当な理由のない団体交渉の拒否(同条第2号) [例] ・ 当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否 ・ 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交) c 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(同条第3号) [例] ・ 労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉を行うこと ・ 労働組合の運営経費に経理上の援助を与えること d 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(同条第4号) [例] ・ 労働者の労働委員会への申立てを理由とする不利益取扱い ・ 労働委員会の調査 ・ 審問において、労働者が証拠を提出したり、発言したことを理由とする不利益取扱い |
出典)厚生労働省「労働委員会」p.5
不当労働行為を行った場合、労働委員会から不当労働行為の停止、原状回復、損害賠償などの救済命令が出されることがあります。また、悪質な場合には、刑事罰が科される可能性もあります。
【注意!】労働組合法の不当労働行為の事例
労働組合法の不当労働行為の事例をいくつか紹介します。
| 不当労働行為の種類 | 具体的な行為 |
| 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い (労働組合法第7条第1号) | 1. 会社が、労働組合の組合員であることを理由として、従業員を解雇した。 2. 会社が、労働組合の役員であることを理由として、従業員の降格処分を行った。 3. 会社が、労働組合のストライキに参加したことを理由として、従業員を解雇した。 4. 会社が、採用試験応募者に対し、労働組合に加入しないことを採用の条件として提示した。 |
| 正当な理由のない団体交渉の拒否 (労働組合法第7条第2号) | 1. 会社が、労働組合の要求を受け入れる意思がないから交渉を行っても無意味であるとのみ述べて、労働組合の団体交渉申入れに一切応じなかった。 2. 会社が、労働組合の団体交渉の申入れには応じたものの、合意した開催予定日直前に期日の延期を申し入れることを繰り返し、結局、団体交渉は一度も行われなかった。 3. 会社が、労働組合との団体交渉において、毎回、要求事項については検討するとのみ答え続け、結局、特段の説明なく、労働組合の要求について検討の余地がないとして団体交渉を打ち切り、それ以降の団体交渉申入れに一切応じなかった。 |
| 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助 (労働組合法第7条第3号) | 1. 会社の代表者が、従業員を集めた会合で、労働組合を批判する発言を行った。 2. 会社の管理職が、部下である労働組合の組合員に対して、労働組合に加入していると昇進は難しいと述べ、労働組合を脱退するよう勧めた。 3. 会社が、労働組合に対して、活動資金を援助した。 |
| 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い (労働組合法第7条第4号) | 1. 労働組合が行った不当労働行為救済申立ての審査手続に、組合員である従業員が有給休暇を取得して参加したところ、会社が、この従業員に対して、手続きへの参加を理由として減給処分を行った。 |
参考)東京都労働委員会「不当労働行為の事例」
これらの事例はあくまで一般的な状況を想定したものであり、個々のケースが実際に労働組合法違反となる不当労働行為に該当するかどうかは、具体的な状況や背景を総合的に考慮して判断されます。
労働組合法違反によって中小企業にどのようなリスクがある?
労働組合法違反は、中小企業にとって深刻なリスクをもたらします。法的責任だけでなく、社会的信用や従業員との関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
法的リスク(損害賠償、刑事罰など)
不当労働行為が認められた場合、企業は労働委員会からの救済命令に従わなければなりません。これには、不当な行為の停止、原状回復、損害賠償などが含まれます。また、悪質な場合には、刑事罰が科される可能性もあります。
社会的リスク(企業イメージの低下、取引停止など)
労働組合法違反が公になると、企業のイメージは大きく損なわれます。とくに、近年は企業の社会的責任(CSR)が重視されており、労働者の権利を尊重しない企業は、消費者や取引先からの信頼を失う可能性があります。
従業員との関係悪化
労働組合との対立は、従業員の企業に対する信頼を損ない、モチベーション低下につながる可能性があります。また、労働環境の悪化は、従業員の不満を高め、離職率の増加につながる可能性があります。
労働組合法の違反を防ぐために企業ができること
労働組合法違反は、企業にとって大きなリスクとなります。違反を防ぎ、健全な労使関係を築くために、以下の対策を講じることが重要です。
日頃からのコミュニケーション
労働組合との円滑な関係を築くためには、日頃からのコミュニケーションが不可欠です。定期的な意見交換や情報共有を通じて、相互理解を深め、信頼関係を構築する必要があります。
団体交渉への適切な対応
労働組合から団体交渉を求められた場合、企業は誠実に対応する義務があります。団体交渉の場では、労働組合の要求に真摯に向き合い、建設的な議論を行うことが大切です。
事前の適切な準備と当日の議事録などの記録作成も忘れずに行いましょう。
労働組合法に関する知識の習得
労働組合法に関する知識不足は、意図しない違反につながる可能性があります。経営者や人事担当者は、労働組合法に関する知識を習得し、適切な労務管理を行う必要があります。
労働組合に関する疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や労働相談センターなどの相談窓口の活用がおすすめです。
また、労働組合とのトラブルが発生しそうな場合には、すぐに弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
この記事では、労働組合法の基本から、とくに注意すべき不当労働行為、違反した場合のリスク、そして具体的な対策について解説しました。
重要なのは、労働組合法を単なる規制として捉えるのではなく、従業員との信頼関係を築き、企業の成長を促進するためのツールとして活用することです。日頃からのコミュニケーションを密にし、労働組合との建設的な対話を心がけましょう。
もし、労働組合に関する疑問や不安があれば、専門家に相談することも有効です。労働組合法を正しく理解し、適切な労務管理を行うことで、従業員との信頼関係を築き、企業の成長へとつなげられるのです。
関連記事
-

オンライン面接のマナー完全ガイド|服装・背景・通信環境・場所の注意点
しかしオンライン面接は、「移動時間や交通費がかからない」というメリットがある一方で、対面とは勝手が違うため、「どのような服装が適切か」「特有のマナーはあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
気軽に実施できるように思えるオンライン面接ですが、画面越しであっても、服装には配慮すべきですし、「どんな背景を設定するか」「通信環境に問題はないか」といった点も評価に影響する可能性があります。
そこでこの記事では、オンライン面接で意識すべき重要なマナーについて、服装、背景、適切な場所選び、機材の確認といった観点から徹底的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-

離職票をハローワークへ提出しないとどうなる?提出期限や必要なものを解説
退職した人が受け取る「離職票」は、その後の生活において非常に重要な役割を持つ書類です。
特に、失業給付(いわゆる失業保険)の受給手続きには不可欠となります。しかし、離職票を受け取った後、ハローワークへいつまでに提出すればよいのか、もし提出しなかった場合どうなるのか、不安に思う方も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、離職票の種類や発行条件といった基本から、ハローワークへ提出しない場合のデメリット、企業側の手続きなどについて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
-

退職金とは?税金の計算方法や年金の種類、相場まで徹底網羅
従業員の長年の貢献に報いるための「退職金」。しかし、制度設計や資金準備、複雑な税金計算に頭を悩ませている中小企業も少なくありません。
自社に最適な制度や税負担を軽くする方法など、疑問や不安のある中小企業が知るべき退職金のポイントを徹底網羅します。退職金の基本的な仕組みから中小企業が活用しやすい具体的な制度まで、わかりやすく解説します。
-

ハラスメントは何種類?職場における事例と対策を学んで会社を守ろう
ハラスメントとは、職場において従業員の尊厳を傷つけ、就業環境を悪化させる行為のことです。近年、多様なハラスメントが問題視されるようになっています。特に中小企業では、人員や管理体制の関係でハラスメント対策が十分に整っていないケースも多いことが現状です。しかし「企業の信頼失墜」や「訴訟リスク」につながる可能性があるため、対策をしましょう。
この記事では、ハラスメントの基本的な定義、法律上の位置づけ、リスクの影響と防止策・対応策について詳しく解説します。 -
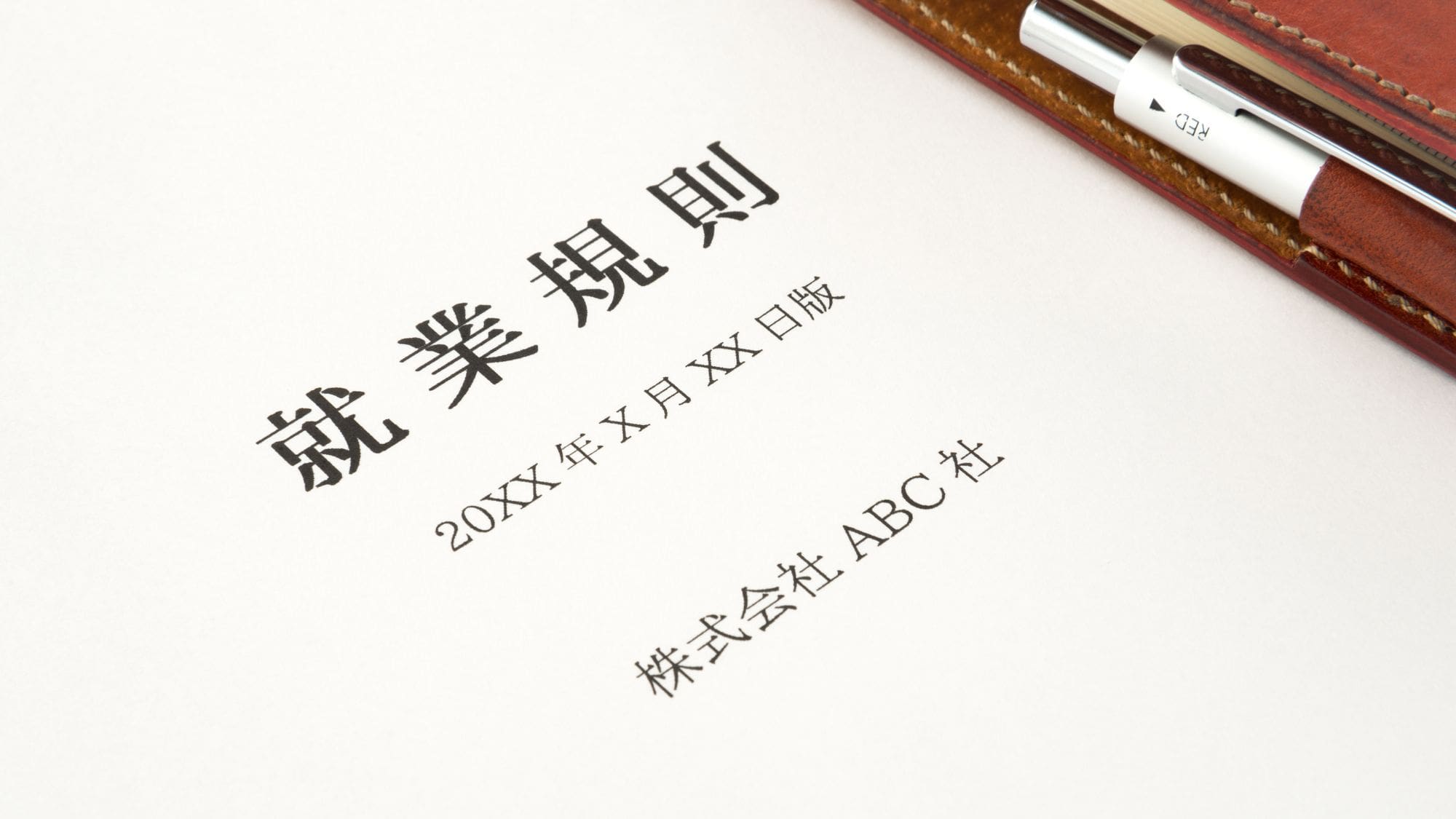
就業規則とは?労働基準法とどちらが優先される?2つの関係を正しく理解しよう
労働者の働き方と企業の経営において、就業規則とは労働基準法と切っても切れない関係にあります。
就業規則とは職場のルールブックとして、労働条件や規律を明確に定めるものですが、その内容は労働基準法が定める最低基準を満たしている必要があるのです。
両者の関係性を正しく理解しないまま運用すると、知らず知らずのうちに法令違反を犯し、労使トラブルや予期せぬリスクに直面する可能性があります。
この記事では、就業規則と労働基準法の基本的な関係から、就業規則に必ず記載すべき事項、作成・変更の手順、違反した場合のリスク、そしてトラブルを防ぐために中小企業ができることまでをわかりやすく解説します。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録