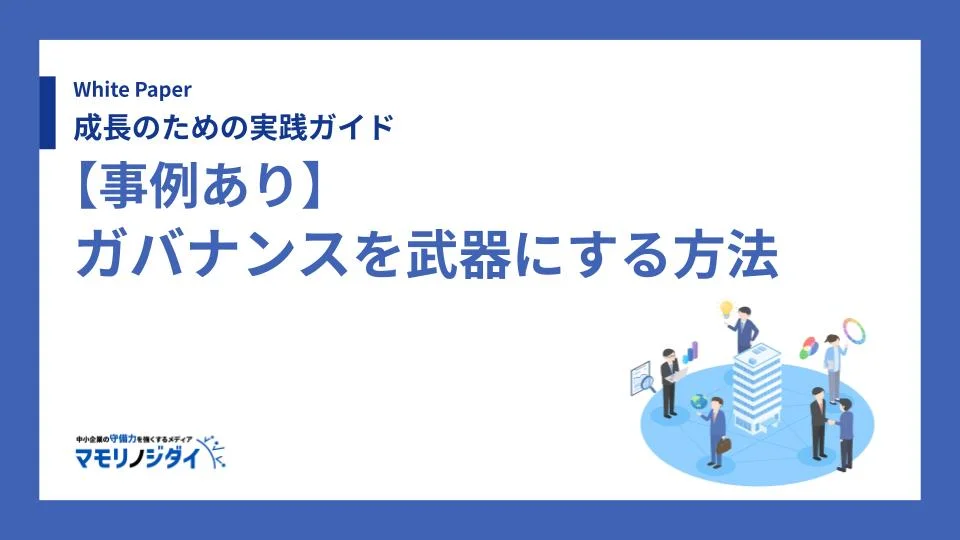法人税法とは?中小企業が受けられる優遇措置や節税方法も解説

「法人税」については漠然と知っていても、法人税法が具体的にどのようなものであるかについてや、効果的な法人税の節税方法などについてはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
企業を経営する上で、法人税法や法人税の節税方法を理解していることは、大きな武器となります。
この記事では、法人税法の基本から、経営に役立つ節税のための具体策などについて詳しく解説していきます。
目次
法人税法とは
法人に課せられる税金には、「法人税」・「法人住民税」・「法人事業税」の3つがあり、これらをまとめて「法人税等」や「法人3税」と呼びます。
法人税法は、上記のような法人が納めるべき税金に関する規定を定めた法律です。
法人税法の第一条には、以下のように記されています。
| (趣旨) 第一条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 |
出典)法人税法
法人税法の目的は、法人に対して公平に課税を行うことです。
- 納税義務者
- 課税所得の範囲
- 税率
- 申告・納付の手続き
これらについて規定されており、法人税の対象となる法人は、法人税法に従って正しく納税しなければなりません。
法人の種類によって法人税が課せられるかどうかが変わる
法人税が課せられるかどうかは、法人の種類によって異なります。
以下の項目では、法人税を支払う必要がある法人と、支払う必要がない法人について解説していきます。
法人税を支払わなければならない法人
一口に「法人」といっても、株式会社や社団法人、財団法人など、さまざまな種類がありますが、以下のような法人はすべて法人税の課税対象となります。
| 普通法人 | 株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・一般社団法人・医療法人(社会医療法人を除く)などの営利を目的とした法人。 |
| 協同組合等 | 農業協同組合・漁業協同組合・消費生活協同組合・信用金庫など、特定の事業や活動を行う法人。 |
基本的に、営利を目的とした法人は、法人税の課税対象になると言えます。
参考)国税庁「法人税の基本的な仕組み」
法人税を支払わなくていい法人
以下のような、営利目的ではない法人の場合、法人税が課税されません。
| 公共法人 | 地方公共団体・株式会社日本政策金融公庫・日本放送協会・日本中央競馬会、日本年金機構など、国や地方公共団体に関わる法人。 |
| 公益法人等 | 社会医療法人・学校法人・NPO法人・社会福祉法人・宗教法人など、公益を目的とする法人。 |
| 人格のない社団等 | PTA・同窓会・同業者団体など、法人でない社団、または財団で、代表者や管理人の定めがある団体。 |
ただし、「公益法人等」や「人格のない社団等」の場合、収益事業から生じた所得は課税対象となります。
参考)国税庁「法人税の基本的な仕組み」
法人税の対象となる所得
法人税の対象となる所得は、「益金」から「損金」を引いた金額です。
- 益金:事業による収益や不動産の売却によって得た収益など
- 損金:原価や販管費など、収益を出すためにかかった費用
なお、益金と損金はあくまで法人税法の考え方であり、企業の会計処理における収益や費用と一致するとは限りません。
「会計上は費用となるものの税務上は損金にならない」というパターンや、「会計上は費用にならないものの税務上は損金になる」というパターンが存在するからです。
したがって、会計上の利益(税引前利益)と法人税の課税所得は異なる概念であることから、税務調整が必要になります。
参考)国税庁「法人税の基本的な仕組み」
中小企業は法人税の優遇措置が受けられる
法人税法における中小企業とは、「資本金または出資金が1億円以下の法人」のことです。
ただし、資本金が1億円以下であっても、資本金5億円以上の大企業の100%子会社である場合などは中小企業の枠から除外されます。
そして法人税は、原則として「23.2%」が課されますが、中小企業の場合は大企業よりも法人税の優遇措置を受けることが可能です。
| 年800万円以下の所得の税率 | 15% |
| 年800万円を超える所得の税率 | 23.2% |
上記の通り、年間800万円以下の所得に対しては、安い税率が適用されます。
参考)中小企業庁「法人税率の軽減」
法人税の計算方法
法人税の税額は、以下の流れで計算することができます。
- 課税所得を算出する
- 適用される法人税率を確認する
- 課税所得に法人税率を掛ける
課税所得は、法人の益金(収益)から損金(経費や損失)を差し引くことで算出できます。
この際、損金不算入や益金加算といった税法上の調整が必要になることもあるので注意しましょう。
次に、適用される税率を確認します。
前述の通り、中小企業の場合は800万円以下の所得に対して優遇措置があるため、それも踏まえた上で売上の金額ごとに適用税率を分けてください。
課税所得と法人税率を割り出したら、「課税所得 × 法人税率」によって法人税額を算出できます。
なお、特定の条件を満たした場合、算出された法人税額から税額控除(研究開発費税額控除や外国税額控除)が差し引かれる場合があります。
参考)国税庁「法人税の基本的な仕組み」
参考)国税庁「No.5759 法人税の税率」
効果的な法人税の節税方法
中小企業の場合、資本面において大企業よりも不安定であるケースが多いです。
したがって、法人税の支払いを可能な限り抑えたいと考えている中小企業も多いでしょう。
この項目では、効果的な法人税の節税方法について紹介していきます。
役員報酬を増額して損金計上する
「役員報酬を損金計上する」という方法は、法人税の節税対策として非常に有効です。
「定期同額給与」や「事前確定届出給与」といった一定の要件を満たした役員報酬であれば、損金として計上し、経費のように課税所得から差し引くことができます。
そのため、役員報酬を上げるほど計上できる損金も増えるため、支払う法人税を減らすことが可能です。
ただし、役員報酬が増えると、役員個人として支払う所得税や住民税などの額も上がります。
したがって、役員報酬を上げすぎた結果、全体の納税額で考えると逆に税金が増えてしまう場合もあります。
そのようなことにならないよう、税理士と相談しながら適切な役員報酬を設定するようにしてください。
参考)国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
福利厚生を手厚くする
福利厚生を手厚くし、かけた費用を損金として計上することも、法人税の節税に繋がります。
福利厚生が充実すれば、企業にとってさまざまなメリットが生まれます。
損金計上できる福利厚生の具体例・メリット・注意点については以下の通りです。
| 健康診断 | 福利厚生に健康診断を組み込むことで、従業員の健康を守ることができる。 |
| 社員旅行 | 企業負担での社員旅行制度を設けることで、従業員のモチベーション向上に繋がる。福利厚生費として計上するには、「旅行の期間が4泊5日以内」「従業員の半分以上が参加」などの条件を満たす必要がある。 |
| 飲食費の補助 | 取引先との飲食費用や、従業員を対象とした新年会・忘年会といった費用を経費として福利厚生費に計上できる。ただし、どこまでが経費として認められるかは大企業と中小企業で異なるため注意が必要。 |
参考)国税庁「第2款 従業員団体の損益」
参考)国税庁「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
参考)国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
赤字を繰り越す
赤字の繰り越しも、法人税対策として有効です。
青色申告をしている法人ならば、最大10年間にわたって赤字分を繰り越せます。
繰り越し分の赤字があれば、短期的に大幅な黒字となった時期があっても、過去の赤字分と相殺できるため、支払う法人税を減らすことが可能です。
また、黒字の翌年に赤字となってしまった場合は、「欠損金の繰り戻しによる還付」を受けることもできます。
ただし、一定の要件を満たす必要があるので、詳しくは下記の国税庁のページを参考にしてください。
参考)国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
不必要な在庫を処分する
不要になった在庫を処分すれば、帳簿に記載する必要がなくなるうえ、処分時の費用を損金として計上できるため、法人税の節税に繋がります。
処分時の費用だけでなく、原価よりも安く売却した場合の差額である「売却損」や、売却できず廃棄した場合の「廃棄損」も、損金計上が可能です。
なお、不要在庫の処分にかかった費用を損金として計上するには、確定申告の際に証明書類を提出しなければならない点に注意が必要です。
参考)J-Net21「居住用と事業用不動産の譲渡損失」
参考)国税庁「第1款 除却損失等の損金算入」
社宅制度を導入する
法人名義で借りた賃貸物件を社宅とし、役員や従業員に貸した場合には、企業側が負担した費用を経費にすることができます。
もちろん、この経費は損金に計上できるため、課税所得を減らせます。
なお、社宅として扱うには、入居者から一定の賃料を受け取らなければなりません。
入居者から賃料を受け取らなかったり、極端に低い賃料を設定していたりすると、従業員側には課税が発生してしまい、企業側も損金に計上できなくなる可能性があります。
賃料設定については、「従業員(使用人)」か「役員」かによって留意すべき点が変わります。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。
出典)国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
出典)国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
損金として確実に計上できるよう、適切な賃料設定を行いましょう。
まとめ
中小企業が安定的な経営を行うには、不測の事態に備えて内部留保を増やしておくべきです。
内部留保を増やすには、法人税の節税が大いに役立ちます。
本記事で解説した節税方法を実行し、資本力の強化を図るようにしてください。
関連記事
-

個人情報保護委員会ってどんな組織?トラブルの際にはすぐ報告を!
個人情報の管理は、中小企業にとって避けて通れない重要な課題です。
万が一、情報漏えいが発生した際には、適切な対応を取らなければ法的責任や信用リスクを負う可能性があります。その際に連携すべき機関が「個人情報保護委員会」です。
本記事では、個人情報保護委員会の役割や企業に求められる報告義務、具体的な対応の流れについて解説します。
中小企業の経営者やバックオフィス担当者にとって、「個人情報漏えい時の適切な報告フロー」を知ることはリスク管理の大前提です。会社の信頼を守るためにも、万が一のトラブルに備えてチェックしておきましょう。
-

残業代の未払いに潜む4つのリスクとは?中小企業が取るべき対処法
近年、働き方改革の推進により、労働者の権利意識が高まり、残業代の未払い問題は社会的に注目を集めています。
とくに中小企業においては、人材不足やコスト削減の観点から、残業時間の管理が曖昧になりがちで、未払い残業代が発生しやすいです。
しかし、未払いの残業代は、企業にとって訴訟リスク、金銭的リスク、信用失墜リスク、人材流出リスクという4つの大きなリスクを抱えることになります。
これらのリスクは、企業の存続を揺るがす可能性も秘めており、中小企業にとって決して看過できるものではありません。
そこでこの記事では、残業代未払いが引き起こす4つのリスクと、中小企業が取るべき具体的な対処法について解説します。
-

契約書のリーガルチェックとは?中小企業が法務リスクを回避する方法
中小企業の経営者やバックオフィスの担当者の中には、契約書や社内規定の法的リスクに不安を感じている方も多いのではないでしょうか?専門知識がない、人手が足りないと、リーガルチェックを後回しにしていると、思わぬトラブルを招く恐れがあります。この記事では、中小企業の実情に即したリーガルチェックの基本から、効率的な実施方法までをわかりやすく解説します。法務リスクから会社を守るためにも、ぜひ参考にしてください。
-

【ひな形あり】中小企業にも有用な内部統制報告書とは?事例、提出方法など
内部統制報告書とは、企業が適切な業務運営を行うための内部管理体制(内部統制)の状況を明確に示すための報告書です。上場企業には提出が義務付けられています。この記事では、内部統制報告書の基本的な定義、ひな形の具体例、不備事例など、必要な情報をわかりやすく解説します。自社のガバナンス体制の整備や適切な内部管理に、ぜひお役立てください。
-
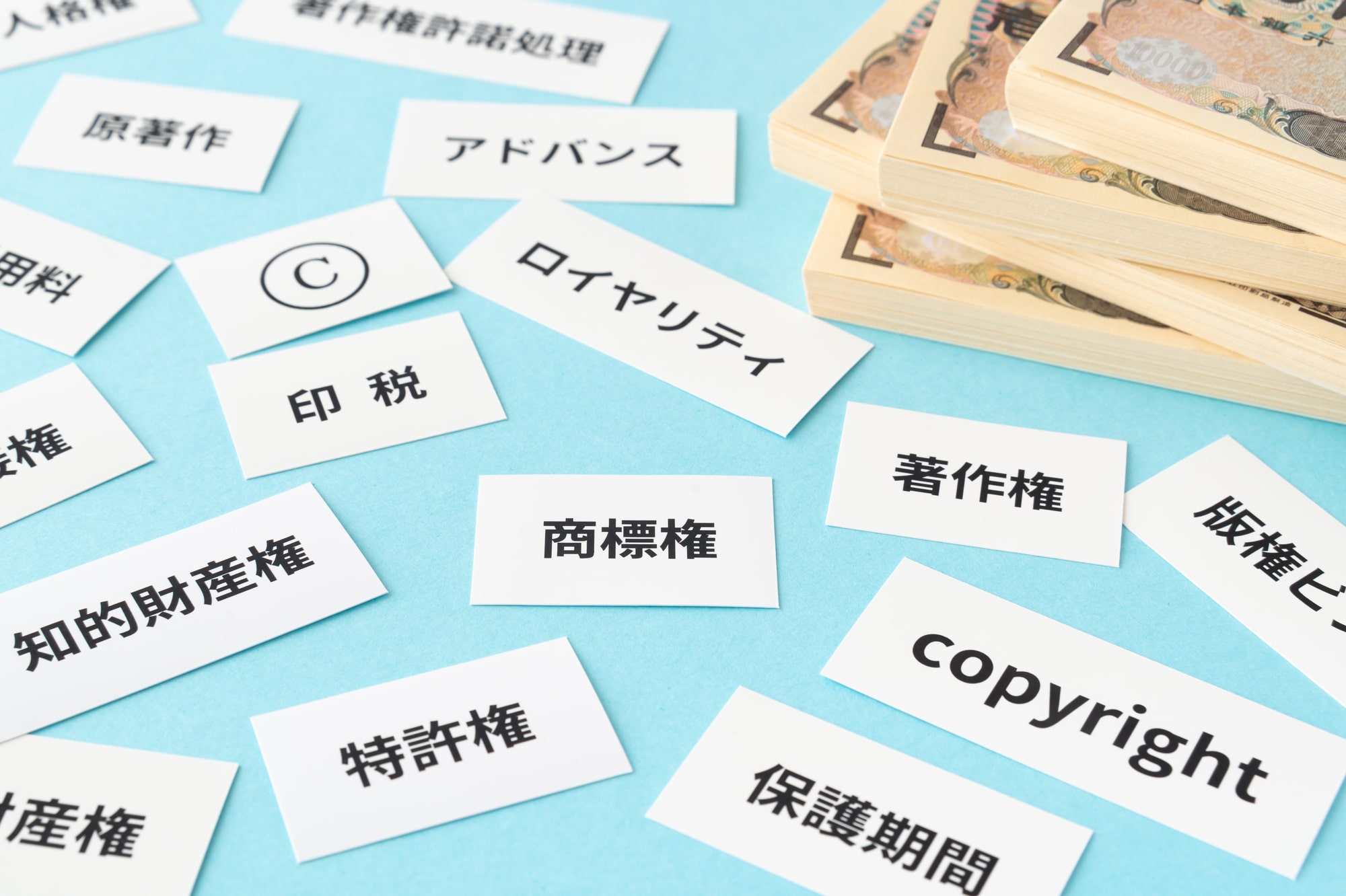
商標法をわかりやすく解説!「知らなかった」じゃ済まされないリスクとは
商標法は、企業や個人が生み出したブランドやアイデアを守り、不正利用を防ぐための重要なルールです。
私たちが日常で目にする商品やサービス名、ロゴ、スローガンなどの多くは、商標として保護されています。しかし、商標法を正しく理解せずに行動すると、意図せず法律違反になることがあります。
他社の商標を知らずに使用した場合や、自分の商標を適切に管理しない場合、商標法違反という思わぬリスクに直面する可能性があるのです。
この記事では、商標法の基本的な仕組みや押さえておきたいポイント、そして「知らなかったじゃ済まない」リスクについて、わかりやすく解説します。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録