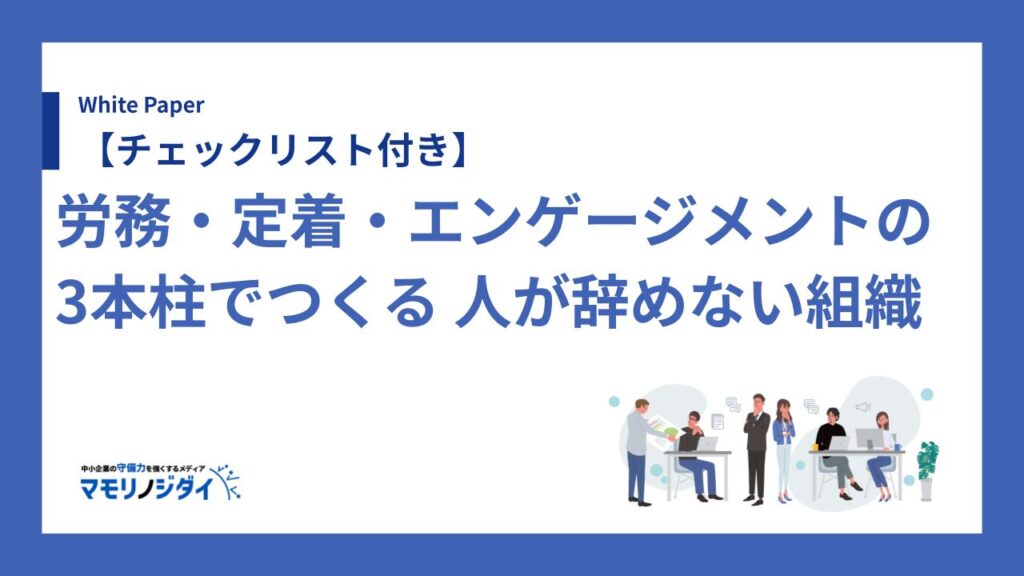【IPOを目指す中小企業は必須】労務DDとは?チェックリストの作り方も紹介
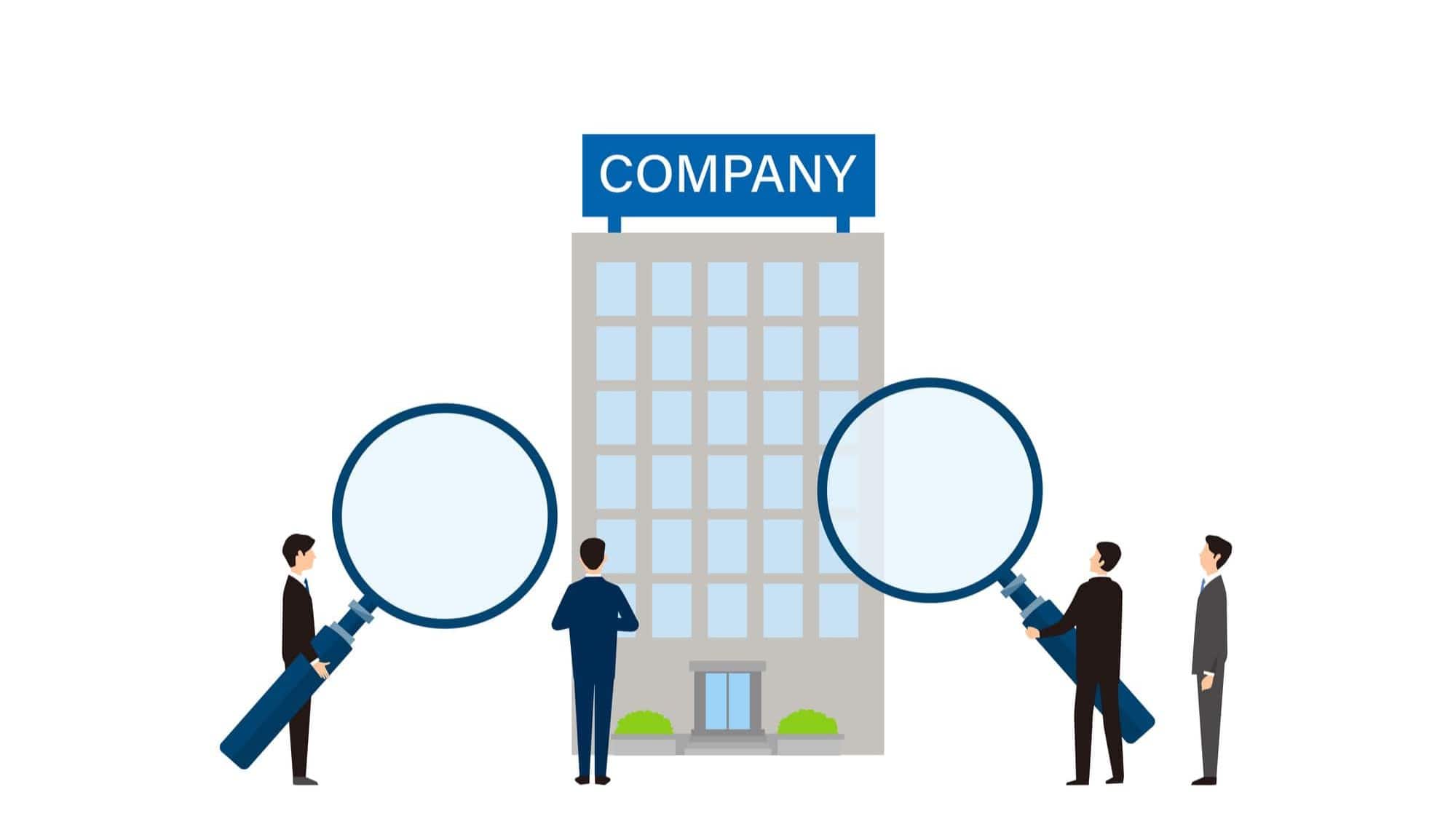
「労務DD」という言葉自体は聞いたことがあっても、具体的に何を指すものなのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、企業経営者や、労務・人事に関わる仕事をしている方の場合、労務DDがどういうものなのか把握しておくべきです。
この機会に、詳細について理解しておくようにしましょう。
この記事では、労務DDにおける基本的な知識から、労務DDが必要なタイミング、労務DDを実施する際のチェックリストなどについて、詳しく解説していきます。
目次
労務DDとは
労務DD(労務デューデリジェンス)とは、企業の労務管理状況を詳細に調査することです。
具体的には、労働契約書や労使協定の適正性、労働時間管理、安全衛生体制、ハラスメント対策などが調査対象となります。
労務DDは、企業の健全性を評価する効果的な手段であり、「社会保険労務士」や「労務・人事に詳しい弁護士」といった外部の専門家によって実施されるのが一般的です。
適切な労務管理が行われていることを証明できれば、投資家や取引先などからの信頼を得ることができます。
労務DDが必要になるタイミング
企業にとって労務DDが必要になるタイミングは、主に以下の3つです。
- IPOを目指す時
- M&Aの予定がある時
- 労務管理のコンプライアンスを高めたい時
IPOを目指す時
IPO(株式の上場)を目指す際には、労務DDが欠かせません。
企業がIPO申請を行う場合、主幹事証券会社や証券取引所によって非常に厳しい審査が行われます。
もちろん、労務環境や人事が適正であるかどうかも審査対象であり、以下のような問題がある場合には上場申請が通ることはありません。
- 未払いの残業代がある
- 何らかのハラスメントがある
- 従業員の安全衛生面への配慮に欠けている
どれだけ資本的な余裕があろうとも、労働基準法を遵守した健全な労働環境が構築されていなければ、IPOは難しくなります。
これからIPOを目指すという中小企業は、労務DDの重要性を早い段階から認識しておく必要があります。
M&Aの予定がある時
M&A(企業の買収・合併)を控えている場合も、労務DDが重要な役割を果たします。
M&Aを検討している企業は、買収・合併の対象となる企業の労務状況について大変敏感です。
M&Aを実施する企業側が、買収・合併先の企業が抱えるリスクをそのまま承継することになるからです。
したがって、「問題のある給与体系」「労働組合とのトラブル」「未払いの残業代」などのリスクを抱えている企業に対しては、M&Aを見送ることも珍しくありません。
労務管理のコンプライアンスを高めたい時
IPOやM&Aといった明確な節目でなくとも、「企業として労務に関するコンプライアンスを高める必要がある」と感じた際には積極的に労務DDを実施すべきです。
労務DDによって、自社の健全性を証明することができれば、従業員たちのモチベーション向上や新たな人材確保といった「企業活動の活性化」に役立つことでしょう。
また、IPOやM&Aの予定がないにも関わらず、自主的に労務DDを実施している企業は多くないため、取引先などに対しても大きな訴求材料になります。
労務DDは、一般的に外部の専門家に委託するので、コストや手間がかかります。一方で、それに見合った効果が期待できることから、企業価値を高める手段として有効です。
労務DDにおける主な調査項目【チェックリスト例付き】
労務DDを実施する際、どのような点に留意すればよいかわからないということもあるでしょう。
この項目では、労務DDでチェックすべき項目について、具体的な例を紹介しつつ解説していきます。
就業規則や関連規程
「就業規則」や「社内規程などの関連規程」は、従業員の義務や権利を明確にして労使間のトラブルを未然に防ぐという目的のために欠かせないルールです。
就業規則等に問題がある場合は、IPOの審査に深刻な悪影響が出るうえ、M&Aの対象となった際にも見送られてしまうリスクがあります。
こうしたリスクを回避するため、労務DDの実施にあたっては、各種規程が法令を遵守したものになっているか入念に確認してください。
【チェックリストの例】
- 雇用形態ごとに就業規則や社内規程が整備されているか
- 各規則・規程が適法か
- 各規則・規程が従業員に適切に周知されているか
参考)厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」
労使協定や労働協約
労働者と企業の間で締結する「労使協定」や「労働協約」が適切であるかどうかも、労務DDにおける重要なチェック項目です。
特に、36協定の遵守は大前提と言えます。
従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、必ず36協定を締結しなければなりません。
| 労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 |
出典)厚生労働省「36(サブロク)協定とは」
また、労使協定や労働協約に合意する労働者代表の選出方法が民主的ではない場合、協定や協約が認められないこともあるという点も注意してください。
【チェックリストの例】
- 労働者の代表がどのように選出されたか
- 時間外労働がある場合、労使間で36協定が締結されているか
- 協定・協約の内容が遵守されているか
労働保険や社会保険
法定要件を満たした従業員は、必ず労働保険や社会保険に加入しなければなりません。
したがって、労務DDでは、各保険への加入漏れの有無について慎重に調査する必要があります。
特に、社会保険は適用対象が拡大されているため注意しましょう。
| 従業員数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、2024年10月から新たに社会保険の適用となります。 |
出典)厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」
【チェックリストの例】
- 各保険への加入状況は適切か
- 保険料が正しく算出されているか
- 保険料が正しく納められているか
安全衛生管理の体制
安全衛生管理の体制がどのようになっているかも、労務DDの重要な要素です。
「従業員の健康と安全」が守られるような環境が整備されているかをチェックし、もし従業員の健康を脅かすような状況が確認されたら、迅速に改善する必要があります。
50人以上の事業所の場合、安全性管理について求められることが増えるため、特に注意しなければなりません。
【チェックリストの例】
- 従業員の健康診断が定期的に行なわれているか
- 産業医の選任状況はどうなっているか
- 労働災害は発生していないか
参考)厚生労働省「1. 安全衛生管理の基本」
ハラスメントの有無
セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど、職場におけるハラスメントはどのようなものであろうと許されません。
仮にハラスメントが存在する企業であることが判明すれば、IPOやM&Aに甚大な悪影響が出てしまいます。
ハラスメントの被害者は、後々の影響を考えて素直に被害を打ち明けられないケースもありますので、労務DDを実施する際にはそのあたりの配慮も必要です。
【チェックリストの例】
- ハラスメントに対する教育は実施されているか
- ハラスメント防止措置は取られているか
- ハラスメントが確認された際の対応は策定されているか
参考)厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
懲戒処分や解雇処分
従業員に対する懲戒処分や解雇処分の規程が定まっているかどうかも、労務DDのチェック項目の一つです。
懲戒や解雇といった重い処分に関して、曖昧な基準になっていれば、労使間で大きなトラブルに発展するリスクを抱えることになります。
就業規則等で処分の基準を明確にすることで、労務に関する問題がないことをアピールできます。
【チェックリストの例】
- 過去にどのような基準で懲戒・解雇処分を行ったか
- 懲戒・解雇処分に対して、過去にトラブルは発生しているか
- 懲戒・解雇処分に対して労使間でトラブルが発生した場合、どのように対処するのか
参考)厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」
未払いの残業代
未払いの残業代は、企業が抱える法的リスクとして非常に大きなものです。
万が一未払いの残業代が発覚すれば、その後従業員との法廷闘争に発展するリスクがあり、IPOやM&Aの大きな障壁となります。
それだけでなく、社会的評価の低下によって、ただでさえ慢性的な人材不足に悩むことが多い中小企業にとって大きな足かせとなることでしょう。
したがって、未払いの残業代関連の問題も、労務DDに欠かせないチェック項目となります。
【チェックリストの例】
- サービス残業が横行していないか
- 名ばかりの管理監督者がいないか
- みなし残業の運用が適切か
労務DDの進め方
労務DDを進める際は、主に以下のような流れで進めていきます。
- チェックリストに沿って労務状況を把握する
- 従業員に対して具体的なヒアリングを実施する
- ヒアリングから浮き彫りになった労務に関する問題点をレポートとしてまとめる
- 問題点・課題点に対する解決策を提案・実施する
まずは、正確に労務状況を把握するために、できるだけ詳細なチェックリストを作るようにしましょう。
次に、従業員に対して行ったヒアリングから見えてきた問題点に対し、どうすれば現状の労務問題を解決できるのかという解決策を導き出します。
労務DDを実施するのは、前述の通り外部の社会保険労務士や弁護士であることが多いため、専門家の意見を大いに参考にしてください。
IPOやM&Aを予定している中小企業は早めに労務DDに取り組むべき
将来的にIPOを目指していたり、大手との合併を望んでいたりする中小企業は、できるだけ早く労務DDに着手すべきです。
特に、好条件でのM&Aはいつ訪れるかわかりません。
その際、買収元の企業は、必ず労務DDを実施します。
しかし、労務DDを実施した結果、「労務環境に問題がある」と判断されてしまえば、せっかく良い条件での合併を希望していた大手企業が、手を引いてしまう可能性もあるのです。
また、IPOに関しても、非常に長い準備期間が必要となるため、早い段階から労務DDを実施すべきです。
まとめ
労務DDは、「中小企業にとって関係がない」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
年々、コンプライアンスが重視されるようになっている現状を鑑みると、IPOやM&Aの予定がなかったとしても、企業としての健全性を訴求するための大きな武器となります。
自主的に労務DDを行っている中小企業は少ないため、他社との差別化を図るためにも、積極的に実施しましょう。
関連記事
-

5Sとは? 目的やメリット、導入ステップとポイントを解説
5Sとは整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、躾(Shitsuke)の5つの日本語の頭文字を取った言葉です。5Sは、効率的な職場管理手法として世界中で広く活用されています。今回は製造業を中心に、生産効率向上やコスト削減などさまざまなメリットがもたらす可能性にも焦点を当てながら5S導入のポイントを紹介します。
-

ゼロエミッションとは?効果、具体例、補助金、日産の事例など
ゼロエミッションとは「温室効果ガスの排出量をゼロにすることを目指す取り組み」を指します。持続可能な社会を実現するために必要な取り組みです。この記事では、ゼロエミッションの基本的な考え方、その社会的な効果、企業や自治体の具体的な取り組み事例、補助金情報、具体的なアクションについて詳しく解説します。
-

情報漏洩の有名な事例としてはどんなものがある?事例から学ぶ対処法も解説
デジタル化が進む現代において、企業が取り扱う情報の価値はますます高まっています。
その一方で、情報漏洩のリスクは企業規模を問わず、すべての組織にとって深刻な経営課題となりました。
ひとたび情報漏洩が発生すれば、金銭的な損害はもちろん、顧客や取引先からの信用を失い、事業の継続が困難になることさえあります。
そこでこの記事では、世間を騒がせた有名な情報漏洩の事例を紹介しつつ、中小企業が実践すべき具体的な対処法・予防策などについて詳しく解説していきます。
自社のセキュリティ体制を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。
-

KPIとは何かを簡単にわかりやすく解説!KPIが必要な理由も紹介
「KPIとは具体的にどういう意味?」
「目標達成のために重要らしいけど、どう活用すればいい?」
ビジネスの現場で頻繁に耳にする「KPI」という言葉ですが、上記のような疑問を持っている方も多いはずです。
KPIは、単なるビジネス用語ではなく、組織やチームが着実に目標を達成するための強力な羅針盤となる考え方です。
この記事では、KPIとは何かという基本的な定義から、なぜビジネスにKPIが必要なのかという理由、具体的な職種別の設定例まで、わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-

技術革新とは?事例やイノベーションとの違いをわかりやすく解説
技術革新は、日々の生活やビジネスに大きな影響を与える変革です。この記事では技術革新の意味や歴史、もたらすメリットなどについて詳しく解説していきます。企業や社会で技術革新は、イノベーションと同じように扱われます。どのような違いがあるのか、具体例を交えながら掘り下げていくので、理解を深めて活用方法を考えていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録