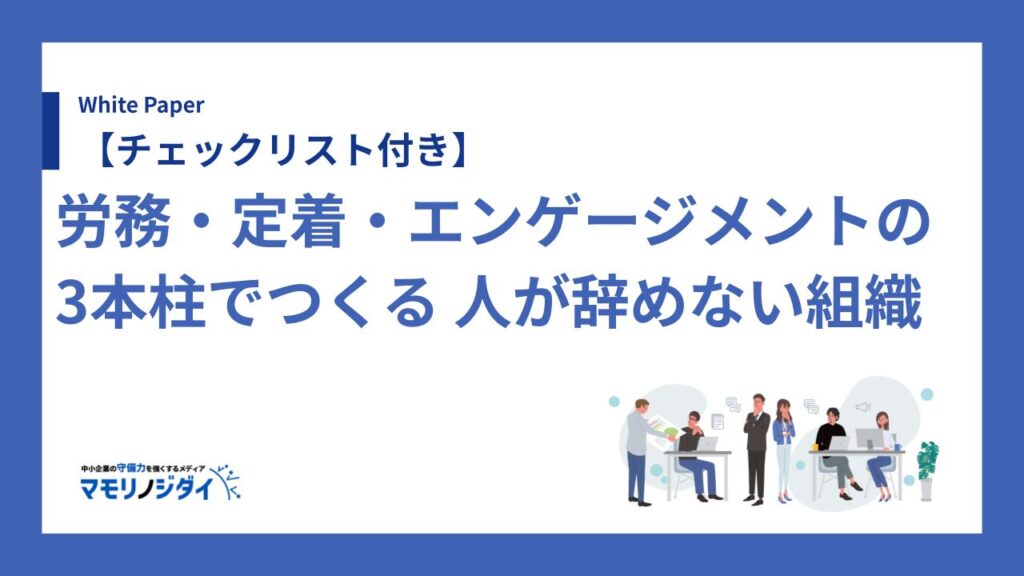学生アルバイトを雇用している企業必見!103万円の壁撤廃で学生の扱いはどう変わる?

103万円の壁が撤廃されることで、アルバイトをしている学生の状況も大きく変わります。
もちろん企業側も、「何がどう変わったのか」について把握しておかなければなりません。
しかし、103万円の壁が撤廃されることは知っていても、具体的な影響や取るべき対策についてよくわからないという方もいるでしょう。
そこでこの記事では、学生アルバイトを多く雇用している企業が悩みがちな点や解決策について詳しく解説していきます。
目次
学生アルバイトに立ちはだかる年収の壁
年収の壁はいくつも存在します。
その中でアルバイトをしている学生が影響を受ける壁は、基本的に以下の4種類です。
- 100万円の壁
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
それぞれ、詳しく解説していきます。
100万円の壁
100万円の壁とは、住民税の支払いが発生する年収のことです。
自治体によっては、課税ラインが「93万円超」「97万円超」となっていることもあります。
住民税を払うことになっても、親の扶養からは外れないことから、世帯の年収にはほとんど影響を及ぼしません。
100万円を多少超える程度の年収ならば、住民税の支払い額も年間1万円弱であるため、100万円の壁についてはあまり意識しないという学生も多いでしょう。
参考)厚生労働省「年収の壁について知ろう」
103万円の壁
103万円の壁とは、所得税の支払いが発生するうえ、親の扶養からも外れる年収のことです。
後述する「勤労学生控除」を受けている学生は、年収103万円を超えても所得税がかからないものの、扶養控除の対象外となってしまうことから、世帯の収入に影響が出てしまいます。
しかし103万円の壁については、2024年12月に閣議決定した「改正税制大綱」により、123万円まで引き上げられることになっています。
参考)厚生労働省「年収の壁について知ろう」
106万円の壁
106万円の壁とは、特定の条件を満たした場合に社会保険への加入義務が発生する年収のことです。
基本的に、学生は106万円の壁の対象とはなりません。
しかし、休学中の学生や、夜間の大学に通っている学生など、一部の条件に該当する学生は106万円の壁の対象となり、社会保険に加入する必要があります。
なお、106万円の壁は2026年10月を目途に撤廃される予定です。
参考)厚生労働省「年収の壁について知ろう」
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険への加入が義務付けられる年収のことです。
学生の場合は、年収130万円を超えた時点で親の社会保険の扶養に入れなくなるため、社会保険料を自分で支払う必要があります。
社会保険料は労使折半とはいえ、負担率が高いことから、130万円の壁を超えないようにシフトを調整する学生アルバイトが数多く存在します。
参考)厚生労働省「年収の壁について知ろう」
学生の税金に関する主な控除
学生関連の税金には、「勤労学生控除」「特定扶養控除」という控除が用意されています。
それぞれの控除について、以下の項目で解説していきます。
勤労学生控除
| 納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。 |
出典)国税庁「No.1175 勤労学生控除」
勤労学生控除とは、学生がアルバイトなどで得た所得に対して一定の所得控除を受けることができる制度です。
具体的には、以下の条件を満たす場合に適用されます。
- アルバイトやパートなどで得た所得があること
- 合計所得金額が75万円以下であること(給与所得以外の所得が10万円以下)
- 学校教育法に規定される学校などに在籍していること
勤労学生控除によって、所得金額から27万円が控除されるため、所得税や住民税の負担が減ります。
その結果「手取りが増える」という点が、勤労学生控除を受ける最大のメリットです。
特定扶養控除
特定扶養控除は、学生ではなく、学生を扶養する親が受けられる恩恵です。
まず扶養控除とは、以下の条件に該当する親族がいる場合に受けられる控除です。
| (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 |
出典)国税庁「No.1180 扶養控除」
扶養控除に該当する親族がいる場合、世帯主は所得税38万円・住民税33万円の控除を受けることができるため、支払う所得税や住民税を減らすことができます。
さらに、以下の「特定扶養親族」に該当する場合は、特定扶養控除として所得税63万円・住民税45万円の控除を受けることが可能です。
| 控除対象扶養親族のうち、平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳未満の方) |
出典)国税庁「◆特定扶養親族」
しかし、子供の年収が103万円を超えると扶養控除・特定扶養控除を受けられなくなってしまいます。
学生本人に関わるものではないものの、世帯の収入に大きく影響を及ぼすことから、扶養控除や特定扶養控除を受けられるラインについて意識している学生も多いはずです。
103万円の壁廃止に伴い「特定親族特別控除の新設」が実施される
従来までは、子供が「103万円の壁」を超える年収を得ることで、親が特定扶養控除を受けられなくなっていました。
そのため、アルバイトをしている学生は働き控えをする傾向にあったことから、学生アルバイトを多く雇用していた中小企業にとっては悩ましい問題だったのではないでしょうか。
そうした悩みを抱えていた中小企業にとって朗報となるのが、「特定親族特別控除(仮称)の新設」です。
103万円の壁廃止に伴い、扶養に関する壁が大きく変わる予定なのです。
「特定親族特別控除(仮称)」の新設により、今まで子供の年収が103万円を超えると適用外になっていた特定扶養控除が、150万円までならば適用されることになりました。
さらに、子供の年収が150万円を超えても、年収188万円までは段階的に控除されることで、親の負担が軽減されます。
親への影響を気にして労働時間を調整している学生も多いため、103万円の壁廃止に伴うこうした変更は、学生アルバイトの働き控え解消に繋がります。
「103万円の壁撤廃」と「特定親族特別控除の創設」に際して中小企業が留意すべきこと
大企業に比べ、学生をアルバイトとして雇用していることが多い中小企業にとって、103万円の壁撤廃に伴うこの度の改正については敏感になるべきです。
この項目では、年収の壁に関する今回の変更について、中小企業が留意すべき点を詳しく解説していきます。
学生アルバイトに周知する
最も大事なのは、アルバイトとして雇用している学生に対し、103万円の壁撤廃に付随する税制上の変更点を徹底的に周知することです。
103万円の壁が引き上げられたというニュースを知っている学生は多くとも、その詳細を把握している人は少ないでしょう。
具体的に、「どれくらいまで働いても親に迷惑がかからないのか」「自分の年収がいくらになると手取りが減るのか」という点について知りたい学生は多いはずです。
そういった要望に応えるためにも、何らかの形で学生を中心とした従業員に対して徹底周知を実行するようにしてください。
人件費の増加に備える
大企業ほどの労働環境を用意しづらい中小企業は、人手不足に苦しむことも多いです。
しかし、103万円の壁撤廃や特定親族特別控除の創設により、これまでに比べて多く働けることを理解した既存の学生アルバイトたちは、より多く働いて収入を増やそうと考えるはずです。
その結果、人手不足の問題は大きく改善することでしょう。
ただ、中小企業は大企業ほど潤沢な資金があるわけではありません。
そのため、早い段階から資金計画を立て、増加する人件費に対応できるようにしておく必要があります。
業務効率化を図って生産性を向上させたり、無駄なコストをカットしたり、といった施策を実行し、人件費の増加に備えておくべきです。
給与の計算システムを見直す
従業員の給与計算について、ITシステムを導入している場合は、103万円の壁廃止によって変更となる部分の対応を忘れないようにしてください。
所得税の課税ラインが変わることで手取りも変更となりますし、扶養に関する計算を行っているシステムならば、その点についての改修も必要になります。
したがって、システムを管理しているベンダーに、年収の壁変更に際して万全の対応をしているのか確認しておくべきです。
そのうえで、源泉徴収や年末調整といった処理が正確に行われるかのテストを、自社でも入念に実施しておくようにしましょう。
まとめ
103万円の壁が廃止されることで、アルバイトをしている学生の労働力上昇が期待できます。
とはいえ、変更された制度の内容を深く理解していない学生も多いので、企業側が主導して学生アルバイトのリテラシーを高めていく必要があります。
手間はかかるものの、結果として労働力の向上に繋がりますので、人手不足に悩んでいる中小企業は積極的に周知していきましょう。
関連記事
-

中小企業が知っておくべきハラスメントの種類一覧!人材と企業をリスクから守ろう
近年、企業におけるハラスメント問題が大きな注目を集めています。特にリソースの少ない中小企業では、多くの経営者が頭を悩ませている問題です。この記事では、中小企業の経営者やマネージャーの皆様に向けて、職場で起きがちなハラスメントの種類を紹介します。具体例を交えながら解説しますので、参考にしてください。
-

フィードバックの意味とは?ビジネスでの活用法をわかりやすく解説
ビジネスの場面でフィードバックが必要だとわかっているものの、適切な伝え方がわからず苦労している方も多いのではないでしょうか。本記事では、マネージャーやリーダーの方に向けて、フィードバックの基本的な考え方や実践的な手法、注意点などを解説します。
-

【中小企業向け】タレントマネジメントとは?導入メリット・成功事例・実践ステップを解説
少子高齢化による労働力人口の減少や、働き方の多様化が進む現代。
企業において、人材は非常に重要な経営資源です。
特に、リソースが限られる中小企業にとって、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織の成長につなげることは喫緊の課題といえるでしょう。
「優秀な人材が定着しない」
「次世代のリーダーが育たない」
「従業員のスキルを把握しきれていない」
このような課題を解決する戦略的な人事手法として、「タレントマネジメント」が注目を集めています。
そこでこの記事では、中小企業の視点に立ち、タレントマネジメントの基本的な意味から、導入する具体的なメリット、実践的な4つのステップ、さらには成功事例までをわかりやすく解説します。
-
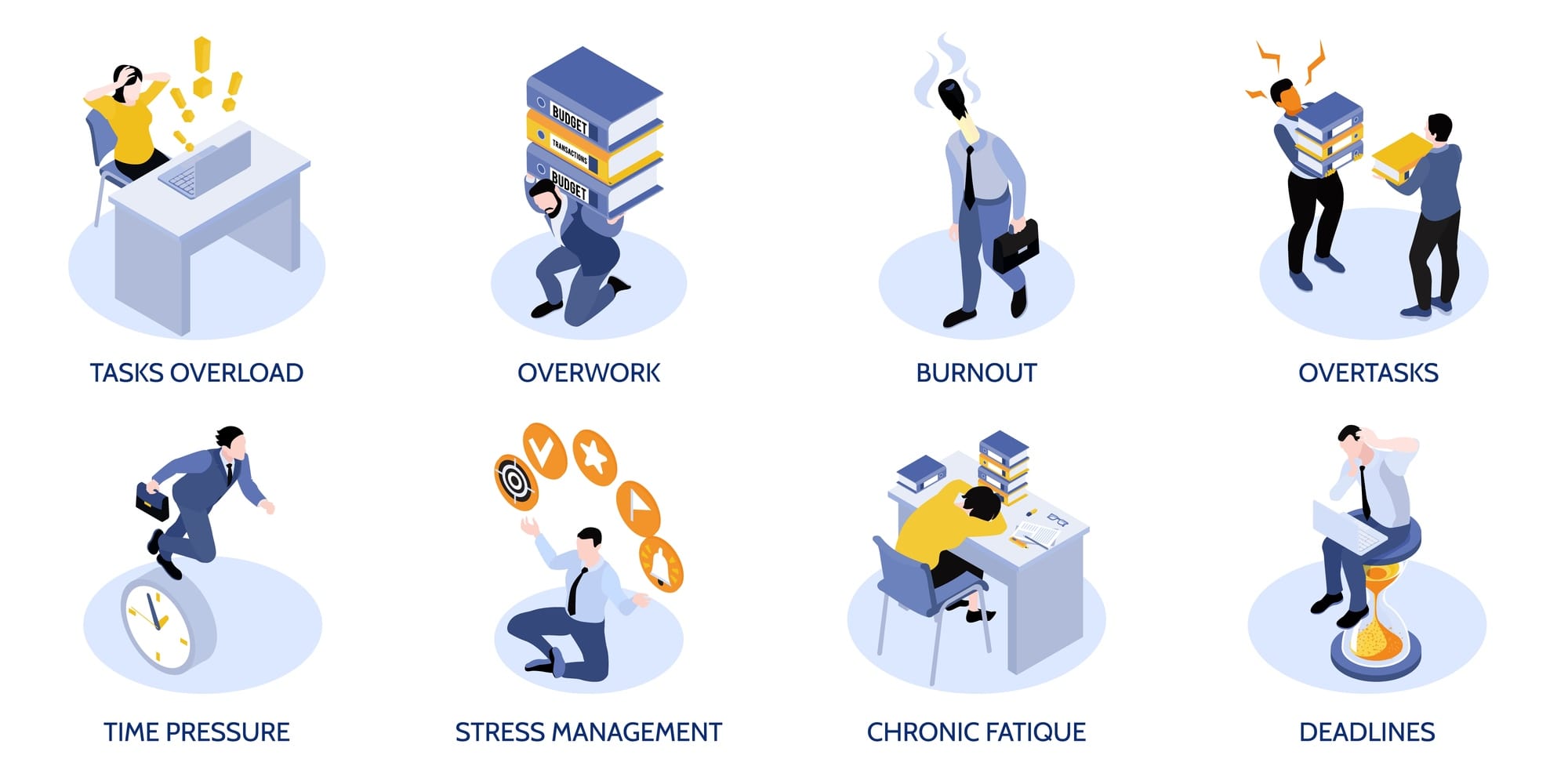
労働条件の不利益変更は適切に!安全に進める方法、手続きを解説
企業が成長・存続するためには、労働条件の変更を検討せざるを得ない場面があります。しかし、労働条件の「不利益変更」は、法的なルールや手続きに則って実行しなければいけません。
特に中小企業では、「合意を取らずに変更した」「説明が不足していた」などの初歩的なミスが大きな問題に発展するケースがあります。知識を理解して、注意することが必要です。
本記事では、「労働条件の不利益変更」に関する基本知識・実務ルール・進め方・注意点を解説します。中小企業の経営者やバックオフィス担当の方は以下を押さえておきましょう。
-

ストレスチェックで職場の健康を守る!中小企業で義務化になった点など
近年、注目されているのが「職場でのメンタルヘルス対策」です。特に中小企業では、従業員の心の健康が会社の成長に直結するため、効果的な対策が求められています。この記事では、ストレスチェックの基本から実践的な導入方法まで、中小企業の経営者やマネージャーの皆さまにわかりやすく解説していきます。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録