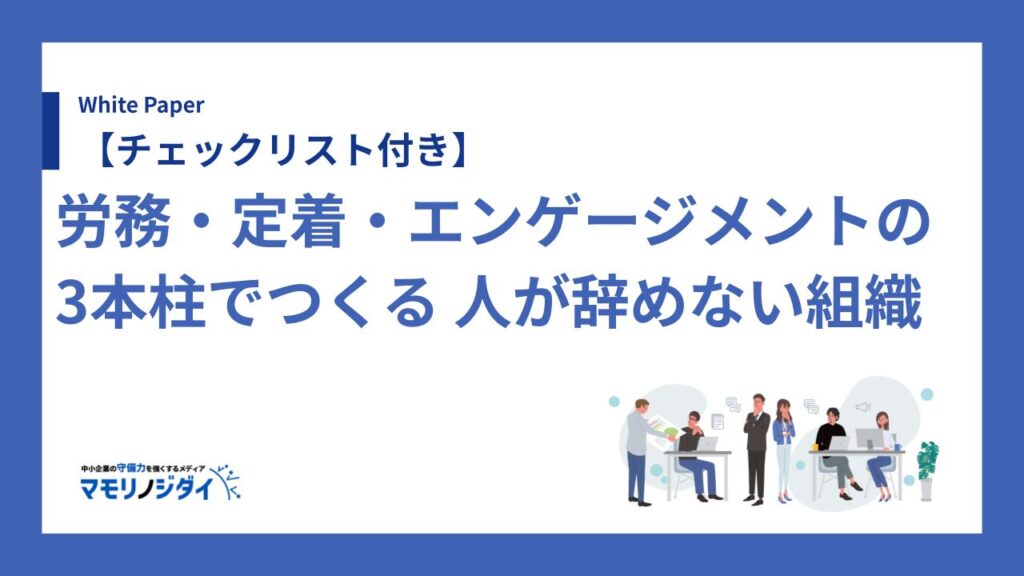労働基準監督署に相談されたらどうなる?中小企業が知っておくべきポイント

中小企業にとって、労働基準監督署への相談は避けたいトラブルの一つです。労働環境や法令の遵守が不十分だと、従業員から労働基準監督署に問題が申告され、調査や是正指導が行われる可能性があります。
こうした事態を防ぐためには、労働条件の明確化や適切な労務管理、従業員とのコミュニケーションなどの取り組みが必要です。
この記事では、労働基準監督署への相談を未然に防ぐための具体的な方法をわかりやすく解説します。
目次
労働基準監督署とは
労働基準監督署は、労働基準法や関連法令の遵守を監督・指導する国の機関で、労働者が安全かつ適切な環境で働けるよう、労働条件や労働環境の改善を推進します。
企業に対しては、法律違反の是正や労働者の権利保護を求め、指導や調査を行います。
また、労働者からの相談・申告に基づき、企業への調査や対応を進めることが重要な役割です。
参考)厚生労働省「労働基準監督署の役割」p.1-2
労働基準監督署と似たような名称を持つほかの機関に、労働基準局、都道府県労働局があります。これらの違いを以下の表にまとめたので、確認してみてください。
| 名称 | 役割 | 管轄範囲 | 具体的業務 |
| 労働基準監督署 | 労働基準法などの法令に基づき、現場レベルで監督・指導 | 市区町村 | ・事業所への立ち入り調査 ・労働災害発生時の調査 ・労働条件の違法状況是正指導 |
| 都道府県労働局 | 労働基準監督署を管理・指導し、管轄内の労働行政全般を統括 | 都道府県 | ・労働基準監督署への指導や支援 ・労働相談窓口の運営 ・雇用関係や労働問題解決に向けた調整業務 |
| 労働基準局 | 労働政策の策定や全国的な基準の統一を図る厚生労働省内の部署 | 全国 | ・法改正や通達の作成 ・全国的な労働基準行政の運営方針の決定 ・統計データの分析と発表 |
参考)厚生労働省「労働基準行政の組織と仕事」
このように、労働基準監督署は現場監督、都道府県労働局は地域全体の管理、労働基準局は全国的な方針策定と、それぞれ役割が異なります。
労働基準監督署の役割を理解することで、企業として適切な対策を講じ、労務トラブルを未然に防ぐことが重要です。
労働基準監督署に相談される主なトラブル
労働者がどのようなトラブルで労働基準監督署に相談するのかを把握し、事前に対策を講じることが求められます。
以下で主な相談事項と労働基準監督署の対応についてをまとめました。
| 相談事項 | 内容 | 労働基準監督署や法的な対応 |
| 賃金未払い | 労働時間に対して賃金が支払われない、残業代の未払いなど | 労働基準法違反であり、労働基準監督署が立ち入り調査を行う可能性あり 事業者に是正指導が行われ、未払い分を請求される場合が多い |
| 36協定なしでの長時間労働 | 36協定未締結で法定労働時間を超えた労働の強要 | 法律違反であり、労働基準監督署が36協定の提出を要求し、改善指導を行う 重大な場合には罰則や企業名の公表の可能性 |
| 差別的な解雇 | 性別・宗教・思想などを理由に不当解雇 | 労働基準監督署では一部対応可能 損害賠償や職場復帰は労働局や弁護士への相談が推奨される |
| 休憩時間がない | 労働基準法で定められた休憩時間を与えない | 労基法違反であり、労働基準監督署が調査し、是正指導が行われる可能性 |
| 有給休暇を取れない | 法で定められた有給休暇の取得拒否、妨害 | 違法であり、労働基準監督署が介入して指導を行う場合あり |
| 退職違約金などの発生 | 退職時に不当な違約金を請求、または退職妨害 | 労働基準監督署は違約金請求が不当か調査を行うことがある 具体的な交渉や請求には弁護士相談が必要なケースあり |
| 退職したいのにやめられない | 退職届の拒否、退職後の強制労働 | 法律違反であり、労働基準監督署で対応可能 ただし、民事的な交渉は弁護士への相談が有効 |
| 労働災害に対する放置 | 労働災害が発生しても休業補償、労災保険の手続き等が行われない | 重大な法律違反であるため、労働基準監督署が企業に対応を指導し、労災申請についてもサポートする場合あり |
このように、労働者の不満が労働基準監督署への相談につながっているため、事前に適切な労務管理を行いましょう。
労働基準監督署に相談された後の流れ
労働基準監督署に相談が行われた場合、基本的に中立の立場で調査や指導を行い、労働者の権利保護を目的に行動します。
場合によっては企業に改善を指導し、必要に応じて罰則を科すこともあります。
労働基準監督署に相談された後の手続きや調査の過程を以下にまとめました。
| ステップ | 内容 |
| 1. 相談・申告内容の確認 | 労働者から詳細な状況をヒアリングし、相談内容を確認 場合によっては証拠資料(契約書、給与明細、タイムカードなど)の提出 |
| 2. 労働基準監督署による事実確認調査 | 企業に対して問い合わせ、書類提出指導、現場調査 必要に応じて事情聴取して、違法行為の有無を確認 |
| 3. 是正指導 | 法律違反が確認された場合、企業に対して改善指導を実施 指導内容に基づき、企業は期限内に是正報告書を提出する必要あり |
| 4. 企業の対応確認 | 企業から提出された是正報告書から問題が改善されているかを確認 必要に応じて、追加調査や再度の指導 |
| (必要な場合)5. 罰則・送検 | 重大な違法行為が確認された場合や、企業が指導を無視した場合に、企業やその代表者を送検刑事罰が科される場合もあり |
| 6. 問題解決 | 企業が法律を遵守する状態に戻ることが最終目標 |
もし、労働者から労働基準監督署への相談があった場合には、適切な対応が重要であり、労働基準監督署の指導に対して真摯に対応することが求められます。
労働基準監督署に相談された中小企業が受ける影響
労働基準監督署に相談されることで、中小企業には以下のような影響が生じる可能性があります。
| 影響・リスク | 内容 |
| 調査や是正指導の実施 | 労働基準監督署から調査や違法行為の是正指導が行われ、速やかな対応を求められる |
| 罰則や送検のリスク | 指導に従わなかった場合、罰則や送検、企業名の公表が行われる可能性がある |
| 信頼低下の懸念 | 労働者や取引先からの信頼が低下し、経営や取引関係に悪影響を及ぼす恐れがある |
企業が受ける影響を最小限にするためには、普段から適切な労務管理と社内体制の整備が重要です。
【中小企業必見】労働基準監督署に相談を未然に防ぐ方法
従業員が不満を感じたり、違法な状況が発生したりすると、労働基準監督署に相談されるリスクが高まります。そのため、日頃から従業員の信頼を得られる職場環境を整備し、トラブルを未然に防ぐ取り組みが必要です。
以下で具体的な対策を詳しく解説します。
労働条件を明確にする
雇用契約書や就業規則を整備し、従業員が自身の労働条件を正しく理解できる環境を作ることが重要です。曖昧な契約や口頭での取り決めはトラブルの原因になります。
防止するには、たとえば以下を明文化して周知します。
- 給与や勤務時間
- 休暇の取り扱い
- 評価基準など
これにより、従業員の不要な誤解を防げます。
労働時間を適切に管理する
中小企業でありがちな長時間労働や残業代の未払いは、労働基準監督署から是正指導を受ける主な原因となります。
たとえば、以下の取り組みが防止策となります。
- 36協定を適切に締結し、時間外労働や休日労働を管理する仕組みを整える
- 従業員の業務負担を定期的に見直し、過重労働を防ぐ
- クラウド型の勤怠管理システムを導入するなど
効率的な管理方法を活用しながら取り組むことも効果的です。
賃金や有給休暇を適正化する
残業代の未払いは労働者からの苦情が多い項目です。以下のような取り組みが重要になります。
- 法律に基づいた賃金体系を整備し、時間外労働には適切な残業代を支払う
- 有給休暇を取得しやすい環境を整える(計画的付与制度を活用するなど)
これらの取り組みにより、従業員の満足度が向上し、不満を減らせます。
従業員との定期的なコミュニケーションを図る
従業員の不満や問題を早期に把握し、適切な対応を行うことは、相談リスクを減らすために非常に効果的です。
以下の取り組みが考えられます。
- 定期的な面談やアンケート調査を実施
- ミーティングや懇談会の開催
従業員の声に耳を傾け、改善に努める姿勢が信頼関係を深め、不満やトラブルが発生しにくい職場を実現できます。
労働者の満足度が高まれば、労働基準監督署に相談されるリスクを大幅に減らすことが可能です。
また、労働環境の改善は従業員のモチベーションを向上させ、企業の生産性向上にもつながります。
労働基準監督署以外に労働者が相談できる窓口
労働基準監督署以外にも労働者が相談できる窓口はあります。これらを知ることで、企業側も適切な対応策を立てられるでしょう。
以下に、労働基準監督署以外で労働者が相談できる窓口をまとめました。
| 相談窓口 | 概要 |
| 総合労働相談コーナー | 都道府県労働局が運営する労働問題全般の相談窓口で、匿名での相談も可能 |
| 都道府県労働局の雇用環境・均等部 | 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法など、雇用環境や働き方に関する相談 |
| 労働条件相談ほっとライン | 厚生労働省が設置した電話相談窓口で、労働条件や職場のトラブルに関する相談を受付 |
| 労働組合(ユニオン) | 個人で加入が可能な労働組合があり、不当解雇や労働条件の交渉を代行 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士に労働問題に特化した相談も可能で、費用の立替制度が利用可能 |
| 弁護士 | 労働問題に詳しい弁護士に直接相談 |
このような相談窓口をオープンに提示することで、従業員の安心を高めることもできます。
まとめ
中小企業が労働基準監督署へ相談されることを防ぐためには、日頃から労働環境を適切に整備し、法令を遵守することが重要です。これにより、従業員の不満やトラブルを未然に防げます。
とくに、労働条件の明確化や労働時間の適切な管理は、基本的かつ効果的な対策です。また、従業員との定期的なコミュニケーションを通じて、現場の声を把握し、早期に問題を解決する仕組みを作ることが求められます。
これらの取り組みは、単にリスクを回避するためだけではなく、従業員の満足度を高め、企業全体の信頼性の向上や経営の安定化にも寄与します。
労働基準監督署への相談を回避し、従業員が安心して働ける環境を整えることで、企業の成長基盤を築きましょう。
関連記事
-
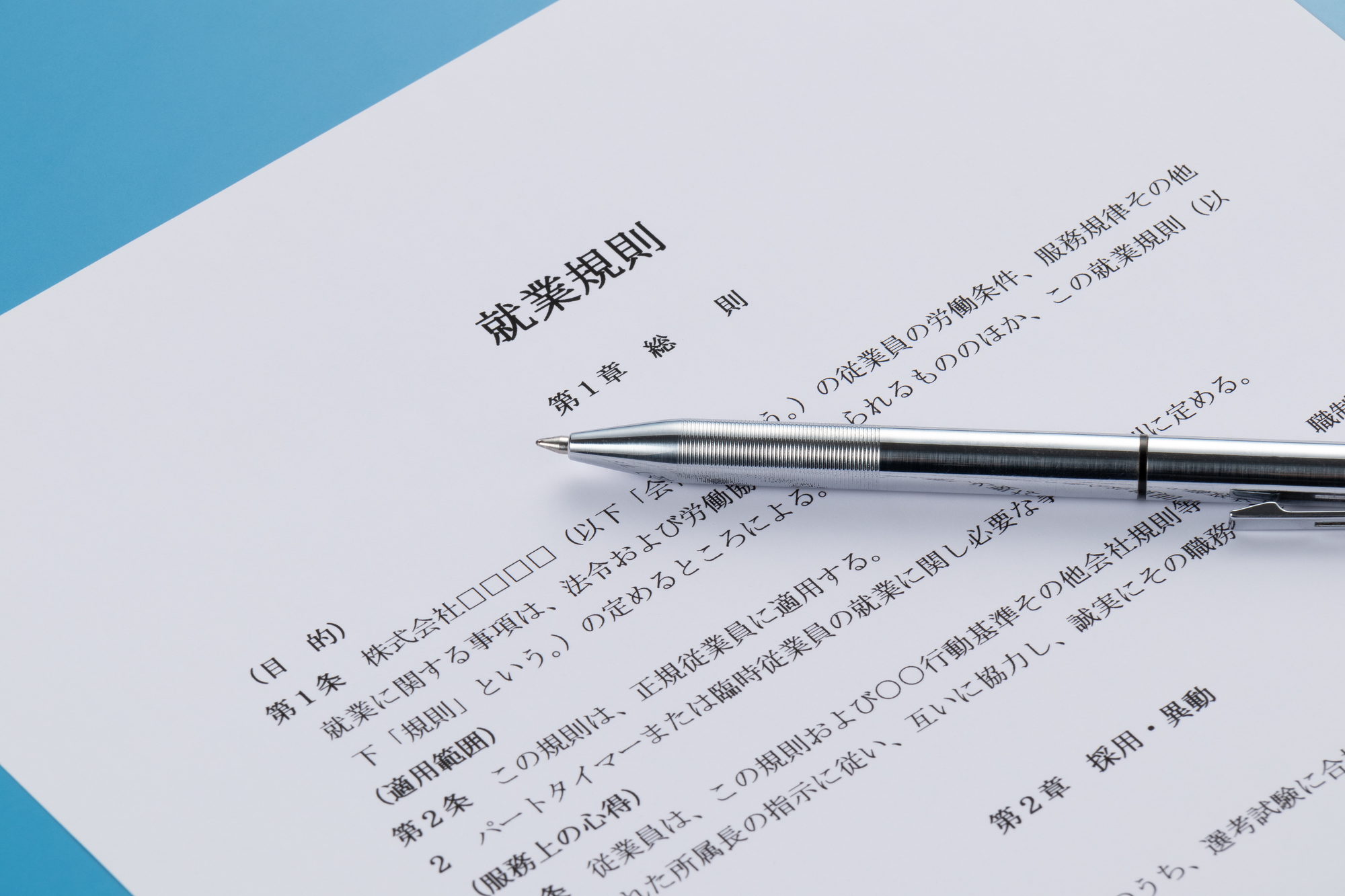
就業規則とは?記載内容や中小企業が注意すべき点をわかりやすく解説
就業規則は、ただ「会社が労働者に守らせたいことをまとめたもの」ではありません。労使間の関係を強化したり、新たな人材確保の機会を得たりするためのツールにもなるのです。この記事では、就業規則に関する基本的な知識をはじめ、中小企業が注意すべき点、効果的な活用方法などについてわかりやすく解説していきますので、是非参考にしてください。
-

アンガーマネジメントで従業員が働きやすい環境を!やり方や役立つ資格
「上司や部下の言動にイライラしてしまう」
「つい感情的に叱責して後悔する」
このような「怒り」に関する悩みは、多くのビジネスパーソンが抱えています。
しかしその問題は、怒りの感情と上手に付き合うためのスキル「アンガーマネジメント」で解決できるかもしれません。
この記事では、アンガーマネジメントの基礎知識から、経営者や管理職が導入することで得られる離職率低下や生産性向上といったメリット、アンガーマネジメントを実践するための具体的な方法などについて詳しく解説します。
「怒り」に関する悩みがある方は、是非この記事を参考にしてください。
-

103万円の壁廃止!中小企業にはどのようなメリット・デメリットがあるのか
2024年末、閣議決定により103万円の壁が廃止されることが決まりました。
しかし、103万円の壁廃止が中小企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか詳しく理解していない、という方も多いでしょう。
そこでこの記事では、103万円の壁廃止による中小企業のメリット・デメリットを中心に、そもそも103万円の壁とは何なのかについてや、中小企業が利用できる公的支援などについて詳細に解説していきます。
-
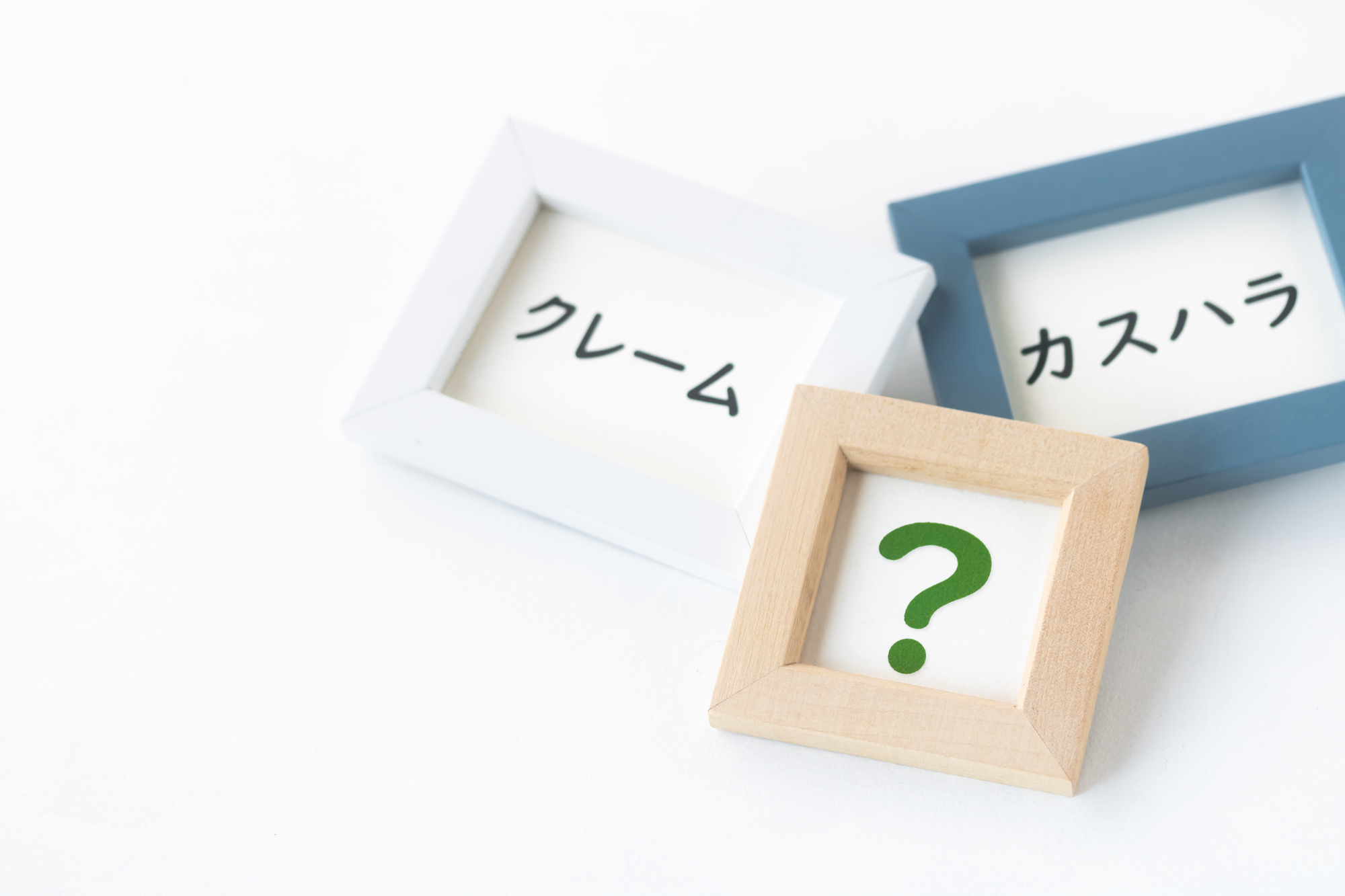
カスタマーハラスメント(カスハラ)から従業員と会社を守る! 対応マニュアル・事例も紹介
「カスタマーハラスメント」は、従業員の心身の健康を損なう問題です。企業の健全な経営にも大きな影響を及ぼします。本記事では、カスタマーハラスメントの具体的な事例や対策、実践的なマニュアルの作り方まで、企業の経営者や管理職の方々に向けて分かりやすく解説します。
-
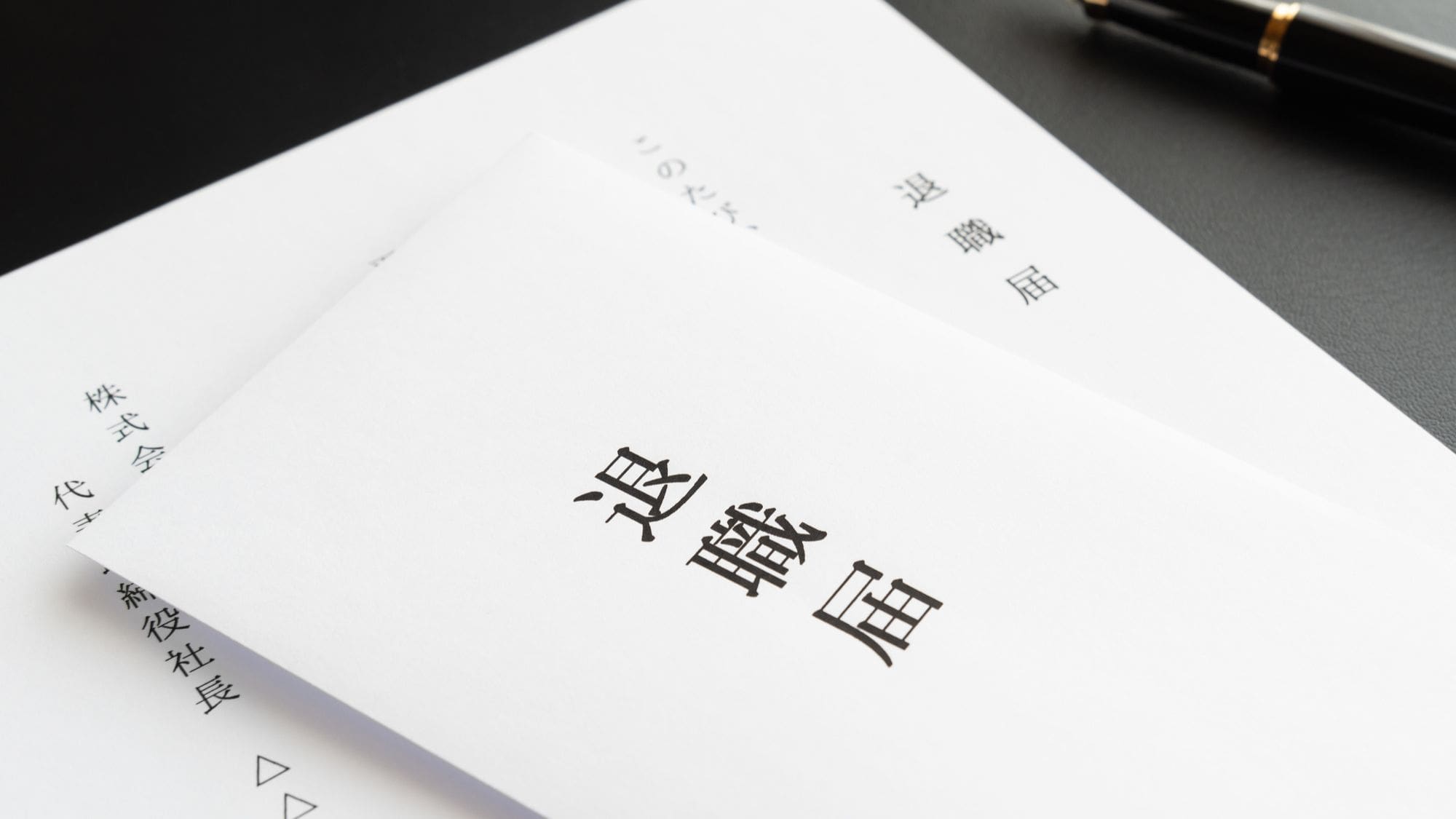
【企業向け】退職とは?種類・手続き・注意点を知ってトラブルを防ぐ
従業員の「退職」は、どの企業でも避けては通れないイベントです。その背景には、さまざまな種類や法的ルール、そして企業が適切に対応すべき手続きや配慮事項があります。
本記事では、退職の定義や種類、法律上のルールから、退職時に企業が行うべき具体的な手続き、注意点までを網羅的に解説。信頼される企業運営のために、ぜひご一読ください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録